謹賀新年
2018/01/05
2017/12/26
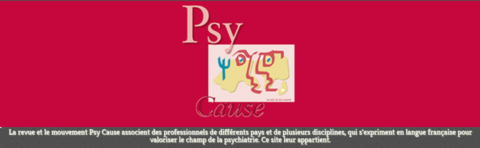
♥ ♥ ♥
2. コートジボアールからの質問
コートジボアールは、以前は象牙海岸と呼ばれたアフリカ西海岸の国だが、字の通りに訳語を当てると、国名が表意的になるので、それを避けて表音的に、コートジボアールと呼ぶことになっている。この国の最大都市、アビジャン Abidjan の大学の女性心理学者から、自身が従事しているらしい依存症、とりわけアルコール依存症の治療に関する質問が来た。このような患者の「社会的自己」が「人間的自己」を取り戻すようにするにはどうすればよいか、治療者として考えているのだが、森田療法からの提案をもらえないかと言うのである。
アビジャンは人口も多く、近代化した都市で、アルコールの誘惑に負ける人たちが少なからずいて、治療に困難を抱えているのであろうと想像できる。したがって、これは尤もな質問である。
しかし、社会教育との関係に立ち戻って、森田療法の本質を取り戻す必要性を言おうとした私の論旨に対して、噛み合うところがない。この質問者が、「社会的自己」と言うとき、社会は、人間が欲望に負ける悪の装置のような意味合いが強い。社会教育と言う場合の社会は、社会悪も含めて、時代により、文化により、変数となりうる社会を、例外なく意味する。厳しいがそう言わざるを得ない。
このアビジャンの質問者は、自分がおこなっている治療法や、そこで工夫していることや、直面している困難について、書いておられない。森田療法は必ずしも、ある精神療法が奏功しない場合に、それに取って代わろうとするものではなく、治療者を励ますものになりうる。また、もしも精神療法を阻む要因が、制度や行政など別のところにあるならば、そちらに目を向けるのもまた、森田療法であろうと思われる。
アビジャンからの質問に齟齬を感じながら、考えを重ねて、長い回答文を書いた。たどたどしいフランス語作文なので、そのままお目にかけられない。書いた作文の要点のみを、日本語に戻して、次に示しておく。
♥ ♥ ♥
3.治療者の「自己教育」について―質問に答える―
森田療法のことに目を留めて頂いたのを感謝します。一見ありふれた質問を頂きました。しかし、ありふれたかに見えるこのような質問こそ、基本的な問題にぶつかるため、答え方に困って返事が遅れてしまいました。
その基本的な難しさは、二段階にわたります。
第一に、問題は森田療法の本質的なところにあります。この療法は、大まかには精神療法の一種ですが、厳密な意味では、人間の教育なのです。創始者の森田自身、療法の教育的な面を強調しました。症状を治すことをこの療法の目的としていず、人間的成長をはかることを重んじています。その成長の体験の中で、症状を治すという課題は、いつの間にか解消していくのです。このような視点から、治療者も患者も、症状を治そうとすることを、忘れねばなりません。しかし、それは治療者患者関係、もしくは師弟関係を破棄することを意味しません。早く症状を治してやろうとする関わりは、優しいが安易な愛にとどまりますが、社会の中で、人格が陶冶されていくのを、根気よく応援し、あまり手助けしない慎重な関わりには、深い教育的な愛があります。
第二には、今日的な問題があります。森田療法を生んだ日本においてすら、上述のような森田療法の本質が軽視され、性急に症状を治そうとする風潮に流されて、森田療法の名の下に、しばしば他の対症療法がおこなわれています。森田療法と他の療法の併用や混合なら、それもいいでしょう。しかし、森田療法と他の療法の混同に至っては、容認し難いものです。
だからこそ、森田療法は、教育、とりわけ社会教育に通じるその本質に回帰すべきなのです。日本においては、歴史的に、西洋から導入された学校教育制度が、社会の中での教育を置き去りにした経緯があり、その教育の危機を救うために、社会の中での学びの復権を目指して、社会教育の気運が高まり、それが継承されてきたのです。ところが、この社会教育も近年低調になるばかりです。
だから、今こそ、森田療法の分野でも、教育の分野でも、社会教育の重要性を想起し、社会教育の復興をはからねばならないのです。
そうは言っても、教育は難しいものです。とりわけ、他人を教育することは困難なことです。それに反して、自分を教育することは、不可能なことではない。そして、自らの教育(自己教育)に打ち込み続けることが、他者に対する教育者あるいは治療者となりうる資質の涵養になります。
例えば、日常生活の中で必要なことをするということは、人間として当然求められることです。より卑近な例として、日常生活の中で、便所掃除は必要不可欠なものです。それをしない者、あるいはそれをしたくない者に、人の教育や治療に当たる資格があるかどうか、言うまでもないことです。
このような答え方に対して、不快に思われるかもしれません。しかし、精一杯に考えて、ここでは率直に答えることにしました。ご賢察願います。
♥ ♥ ♥
4. 便所掃除の復権を求めて
アフリカから届いた質問への答え方を、長い間考えあぐね、返事の作文を練ってメールをようやくあちらに送信した。そしたら、直ちに相手から電報のように短い受信の通知メールが来た。コートジボアールのアビジャンの便所の事情はどうなっているのだろうか。この人は便所掃除をしているだろうか。この奇妙なやり取りは、PsyCause の代表者のボシュア博士も把握しているから、このボスがどのような反応を示すか、見ものである。今のところ、ボスは沈黙を守っている。
一方、日本の社会教育の専門家の方々とやり取りをしているが、こちらにおいても、教育者の自己教育や便所掃除の問題は、いまだに俎上に上らない。小金井の浴恩館で下村湖人が、黙々と便器の掃除をしていた光景を思い浮かべるのは、私だけではなかろうと思うのだが。
2017/11/30
2017/11/23
去る11月上旬、第35会日本森田療法学会が、熊本五高出身者である森田正馬ゆかりの熊本大学において開催された。
1. 五高の奇跡
森田正馬の直弟子で、森田療法を継承した水谷啓二も五高出身者であった。一方社会教育の流れがあって、それが戦後に水谷の森田療法に合流したのだが、その社会教育活動の重要な担い手だった3人の人物、田澤義鋪、下村湖人、永杉喜輔の3人もまた五高出身者だったのである。
剛毅木訥の校風で知られた五高にして、武夫原頭に立つごとく地に足のついた大物たちを生んだのであろうか。
♥ ♥ ♥
2.社会教育という用語について
社会教育という用語がおよそ意味するであろうことの、重要性をわれわれは知りつつ、同時にこの用語につきまとっている不明瞭性を感じざるを得ない。社会教育という四文字は日本語としておさまりが良いけれども、意味は曖昧である。「社会」は形容詞なのか、名詞なのか。形容詞ならば、その意味は、あやふやで捉え難い。ここで思い起こすのは、「対人恐怖」のかつての英訳語、“social phobia”である。これは“social”という形容詞を英語訳に持ち込んだことで本来の意味を晦渋にしてしまった例であった。
社会教育の「社会」が名詞ならば、「社会」と「教育」の関係について説明がなされねばならない。教育の対象としての「社会」であるなら、社会より上位に絶対的な教育者が存在することが前提になるが、それは人間ではなくなる。社会を超越した人間などいないからである。このような意味を帯びるとき、「社会教育」は非人間的なものとなる。
逆に「社会」が人間を「教育」するという意味ならば、わからなくはない。人間は社会の中で育ち、教えられ、学びあって成長していくものだからである。ただし、この場合も、「社会」は人間の集団であるから、個々の成員を疎外するような人間不在の社会集団であってはならないことは勿論である。
わが国においては、社会教育の発生について、それなりの歴史があった。明治の時期に西洋の学校教育制度が導入されたことを背景として、派生的に生じた問題が、その後に社会教育と言われるものにつながっていく。福澤諭吉は、学校教育に対して、人間社会から学ぶという意味で、「人間社会教育」と言った。「社会教育」という用語の始まりであったとされる。ただしこれは来るべき資本主義社会を担う中産階級が、学校教育だけに飽きたらずに、人間社会を学校として、自己教育的に研鑽する必要を説いたもので、より下層の人々を視野に入れるものではなかったと言われる。天は人の下に人をつくっていたようである。その後、学校教育へ向けての就学促進のための親教育や、一般成人に対する教育の必要性も重視されるようになり、それらは「通俗教育」と称された。しかし、教育に恵まれない貧困層を視野に入れる立場から、改めて「社会教育」の必要性が認識されて、「通俗教育」に代わって「社会教育」という用語を大正時代から公的に用いるようになった。
田澤、下村、永杉が関わった社会教育は、戦前におけるこのような歴史的流れに発していた。社会教育と言っても、その「社会」は戦前、戦時下、戦後へと変化して行ったのは当然である。
♥ ♥ ♥
3.社会教育と森田療法の関係について
当初における、社会教育という概念や用語の登場は、その時代の事情に拠るものであったことを、上に述べた。しかし、社会教育における「社会」を、時代に応じた変数と考えれば、曖昧な用語なりに、社会教育を有効語として用いることはできるだろう。また森田療法は、本来教育的な療法であるから、両者が合流し、かつ相互補完的になる可能性は、十分に考えられるであろう。
♥ ♥ ♥
4.「社会教育」の語の外国語訳の難しさについて
先に縷々述べたごとく、「社会教育」の用語の晦渋さを容認して、この語を使用する、いわば“日本的な”立場を取ることにした。しかるに、外国語に訳す段になると、そうはいかず、この用語の曖昧さが再浮上するのである。
フランス語圏のある学会と交流していて、日本の森田療法の最近の事情について、情報を届けて欲しいと、最近強く要望されていた。しかし先般の熊本での学会もあったこととて、その学会のニュースも含めて、森田療法の情報の提供を学会後まで待ってもらった。そして学会直後に、ニュースを書き送った。その中には、社会教育と森田療法に関わる、自分が行った発表についても記しておいたのである。ここで「社会教育」をフランス語でどう書くかが問題であった。適切な訳語がない。やむを得ず、“ l’education populaire “と書いた。しかし案の定、謂わんとする意味が相手に通じない。相手は、曰わく「大変興味があるので、その語が意味するところを詳しく説明してくれないか」。なかなか面倒なことにて困っている始末だ。
♥ ♥ ♥
5.「生活の発見」の「再発見」から「再再発見」へ
ある成り行きから、「生活の発見会」と雑誌「生活の発見」の歴史を調べてみたことがあるのだが、今回改めてそれを辿り直した。そのルーツは水谷啓二氏に遡るものであった。そこにはドラマがあった。水谷氏は熊本五高時代の友人で、社会教育活動をしていた永杉喜輔氏と、再会する。水谷はさらに永杉の師の社会教育者、下村湖人にも出会って、磁石のように吸い寄せられていったのだった。下村は、五高以来の盟友の田澤義鋪に従い、彼の亡き後、社会教育の指導者として道を拓きつつあった。だが宰相下村は昭和30年に没した。水谷は31年に啓心会を開き、翌32年に、雑誌を創刊した。その雑誌は永杉の案により、「生活の発見」と命名され、この雑誌の刊行の趣旨として、森田正馬の生活道と下村湖人の社会教育の両者を継承することが謳われた。雑誌の刊行の主体は、水谷方の「生活の発見会」とされた。
同じ五高出身者たちによる社会教育の流れが、水谷の森田療法に合流したのである。このような歴史を知ることは、すなわち「生活の発見」の「再発見」にほかならない。
まずは、そのような歴史の説明が必要である。しかし、歴史が明らかにしたように、社会教育を摂取した流れの上に立って、森田療法は、今日においてどのように歩を進めるべきだろうか。「再再発見」の課題に直面しているのである。それは、社会教育の今日的課題と、重なるところがあるかもしれない。
日本における社会教育の成立事情は、独特のものであった、という言説により、社会教育という用語の曖昧さと、外国に伝える難しさを言う識者がおられるようである。だが、社会教育も、森田療法も、最も本質的な部分では、国際的に通じ合うようなものがあるのではなかろうか。そう考えて模索しているところである。
♥ ♥ ♥
※ なお、参考までに、第35回日本森田療法学会(熊本)におけるパネルディスカッションで発表した際のスライドを、「研究ノート」欄に提示しようとしています。(本稿より数日ずれる見込み)。
2017/11/16
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
去る11月10日、11日、12日の3日間、熊本大学黒髪キャンパスで開催された第35回日本森田療法学会に参加しました。学会場のキャンパスには、旧制五高記念館の赤レンガの由緒ある建物もあり、歴史のおもむきが漂っていました。五高は、もちろん森田正馬の出身校です。五高生たちの青春に想いを馳せることのできる、そんなキャンパスで開催された学会でした。
熊本は、災害からの復興に取り組んでおられる県でもあり、そんな中で学会開催のご準備をして下さった、大会長の熊本大学保健センターの藤瀬教授やスタッフの方々の御苦労はさぞかし大変だったことと拝察しています。一会員として、感謝している次第です。3日間の会期中は、大会長はじめ、スタッフの方々の温かさのように、天候に恵まれて、快晴の熊本に全国から大勢の会員たちが集まったのでした。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
自分はと言えば、重責ある発表の任を与えて頂きました。五高出身者たちの社会教育の活動が、水谷啓二の「生活の発見」誌とその活動に合流する系譜についての、比嘉千賀先生とのパネルディスカッションでした。事前の抄録は、先に「研究ノート」欄に掲載しました。
パネルディスカッションなるものの、ディスカッションをどうするかは、ケースバイケースでしょうが、不慣れにて、準備に大変困惑しました。まずは、五高出身の田澤義鋪、下村湖人、永杉喜輔の社会教育とはどんな活動だったのか、そしてそれが同じく五高出身の水谷啓二の森田療法にどのように合流したか、歴史的なその内容を皆様にご理解頂けるように説明しなければなりません。それを踏まえてのディスカッションに進むというのが建て前です。でも、社会教育の歴史的流れは、短時間に語るには深過ぎました。それでも、それなりに、短時間で話し切れるように、最初から要約的に伝える工夫をすればできたのかもしれません。その辺の要領が足りなかったようです。時計は容赦してくれません。短時間に沢山詰め込むのは、やはり無理というものでした。予定していた発表の最後の辺りは端折って打ち切るという無様な始末と相成りました。
ディスカッションどころじゃなくなりましたが、幸い前日に比嘉先生とお話しする機会を頂き、そこで事前に「ディスカッション」をすることができました。観客なしの、ノーピープル・ディスカッションですが、そのときに少し自分なりに整理できたことがありました。当日の短時間のディスカッション・タイムでは、その一端を述べました。
それは、集団合宿研修の系譜についてです。医者が中心になると、権威的になりがちなので、ここでは、森田正馬の自宅に入院した原法の集団をも省いて、非医師たちが行った集団合宿の流れを、たどることができました。
まずは、田澤義鋪が大正3年に静岡県の蓮永寺で行った、青年たちの合宿研修が発端としてありました。次に、昭和8年から、下村は小金井の浴恩館で青年団講習所の所長として、合宿指導を行っています。永杉もそこに参加しました。そして戦後に、水谷は啓心寮を開きます。水谷没後、長谷川洋三は龍穏寺で生活の発見会の合宿勉強会を開催しました。その後小田原で和田重正は、はじめ塾や一心寮で、親や子どもたちの合宿を開催したのでした。
♥ ♥ ♥
なお、まず、一般演題として発表した下記について、そのスライドのシリーズに説明を付けて、「研究ノート欄」に掲載しておきます。
「森田正馬が参禅した谷中の「両忘会」と釈宗活老師について」
パネルディスカッションの発表内容は、追って掲載します。
2017/09/16
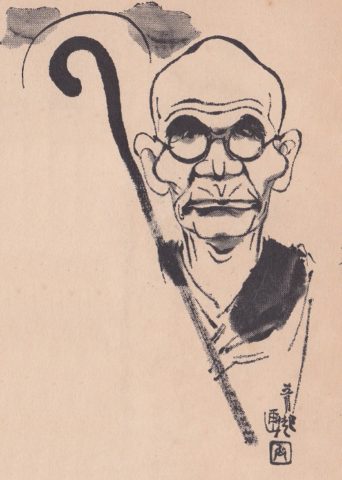
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
1. 異僧、澤木興道
澤木興道は、自坊や自分の家や家族を持たず、各地を行脚して、民衆に参禅指導をした曹洞宗の僧侶で、「宿無し興道」という異名で知られている。日露戦争に出征して、敵兵を斬ったり、撃ち殺したりした経験がある禅僧としても知られる。澤木自身も日露戦争で重傷を負って除隊されたが、その翌年に再度出征している。
森田正馬は、戦争をしかたのない事実と捉え、出征した弟の徳弥に対して、「匹夫の蛮勇を鼓して、敵前の前に進み出て」、犬死にするようなことはするなと諭したのだった。そして徳弥は殉死した。与謝野晶子が弟に、「君、死に給ふことなかれ」という反戦詩を贈った頃のことである。
仏教のうち、禅宗は歴史的に見て右翼的で、国策としての戦争に同調した面があった。
澤木自身は、禅僧として、自身の戦争体験をどうとらえていたのだろう。それを抜きにして澤木興道の禅を考え難い。私はこのような禅僧に危険なものを感じて、関心の外へと排除していた。
ともかく、そんな負のイメージしか伴わない人だったが、ふと知ったことがある。それは、澤木興道が大正の頃に、旧制の熊本五高の学生たちと交流していたことがあり、その体験が澤木の生涯のひとつの大きな転機になったという、意外なエピソードである。
最近、自分は森田療法と社会教育の関係を考える中で、歴史的に、これらの両領域において、幾人もの重要な人物が、森田正馬の母校、熊本五高から輩出している事実を知った。それで五高に注目が及び、調べる中で、五高出身者ではないが、生涯の一時期に熊本に滞在していた澤木興道と五高生の交流のエピソードに出くわしたのである。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
2. 澤木興道、熊本までの半生
澤木興道の熊本での生活は、三十歳代後半から始まる。そこに至るまでの澤木の半生を、まず簡単に辿っておく。
明治13年に、三重県津市で、人力車の金具の製造を家業とする家の4人の子どもの末子として生まれる。4歳のとき母が死亡、7歳のとき父も死亡して、一家離散となり、親戚に預けられたが、その直後にその家の主も急死した。そこで知り合い筋の澤木という男の養子に入った。この澤木は、三重県一身田町の遊郭の裏町で、提灯屋をしながら賭場を開帳しているような人物だった。その界隈は詐欺師、香具師、博徒らの巣窟のような場所だった。小学生で賭場の張り番をさせられた。近所の女郎屋の二階で年配の男が急死した騒ぎがあり、その現場を見に行った。男の死体のそばに茫然と座っている遊女、駆けつけて泣き叫んでいる男の妻女。それを目の当たりにして、子ども心にようやく無常を観じたという。小学校を出ると、提灯の張り替え、寄席の下足番や賭博場でのぼた餅売りなど、日夜あらゆることをした。数十人の侠客連が縄張り争いで斬り合いをしているのを見たこともある。その始末の使い走りを自分が買って出た。
次第にこのような生活環境から出たくなり、家出を重ね、16歳で永平寺まで行って、そこに入れてもらった。翌年、17歳で、永平寺で知り合った僧の紹介で熊本県の天草の宗心寺に行き、澤田興法のもとで出家得度し、以後澤木興道を名乗った。
明治33年、20歳で入営して兵隊となり、兵役の生活が足かけ7年続く。その間、明治37年に出征し、「日露戦争を通じて、わしなども腹一ぱい人殺しをしてきた」という経験をする。戦争が終わり、28歳より足かけ6年、法隆寺勧学院で、唯識学を中心に仏教一般の勉強をした。さらに34歳より足かけ3年、法隆寺の末寺の空き寺の成福寺に住み込んで、独りで座禅ばかりをして過ごした。
そして奇縁により、大正5年、36歳で熊本市の曹洞宗大慈寺に僧堂講師として招かれて、赴任したのだった。この熊本時代に五高生と交流する。大慈寺を出てからも、市内の万日山上の家で居候をした。50歳を過ぎて駒沢大学教授に呼ばれることになるが、それまで熊本を本拠とする生活が長く続いたのだった。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
3.五高生たちとの日々
旧制高等学校の学生たちは、バンカラ、弊衣破帽といった形容で知られる自由奔放な、ユースカルチャーを謳歌していた。それは全国的に共通だったが、とりわけナンバースクールの高校、それも奇数の番号の高校において、独自の特徴があったようである。
熊本五高には、五高独特の校風があり、「剛毅木訥」と言われていた。
そんな五高へ講演に呼ばれたことが、学生たちとの親しい交流の始まりになった。この坊主何を言うつもりか、といった調子で聴きにきた連中に、開口一番「諸君から色気と食い気を除いたら何が残るか」と言ったら、びっくりして彼らは熱心に話を聴き始めた、という。以来学生たちは、大慈寺へ座禅をしに来るようになった。
「和尚さん、座禅は何のためにするのですか」とある学生が訊くので、「座禅をしても何にもならん」と答えたら、ぼやきながら帰ったが、再び姿を現して、「和尚さん、何にもならぬことをしに来ました」と言って座禅を続けるようになった。また、ある学生に、長時間かけて仏教の説明をしてやったが、「なんにもわからん」と言う。女郎屋へ行った帰りに、心境を訴えに来る者もいる。どこへ行くにも、五高生が五人、十人とついてきて、大飯を食うので財布を空にさせられた。
澤木興道は、このような自然児五高生に教えながら学んだということを、弟子による聞き書きの書『禅に生きる澤木興道』の中で言っている。
澤木自身の内面が五高生によって揺さぶられたのである。その辺のことを述べているくだりを、少し長くなるが、次に引用しておく。
「打てば響くように座禅する者があるかと思うと、無茶苦茶に女郎買いする者もおって、その連中が続々やってくるので、兵隊以来、勉強と座禅で神経が細くなっていたわしも、見事に作り直された。いやも応もなく再出発をしなければならなくなって、かえって生き甲斐を感じた。」
「第一、仏教というものに別に用事のない手合いだ。だから、こちらが坊主根性で相手したんでは、てんで話にならぬ。(…)相手は既成宗教的臭みは全然受け付けない。既成概念で片付けようとしようものなら、すぐにそれを剥ぎ取りにくる。素っ裸になって見せないと承知しない。容赦なく素っ裸を強要する。本当のことを言っても、もっと本当のことを言えと言って迫ってくる。だからわしは中途半端なところで糊塗することができなかった。こちら側に少しでも作りものがあると、とことんまで剥ぎ取らないと承知しないお客様である。そこで、自分を取り繕うことは、わしはできぬようになった。また自分というものを作ってはならぬと思うようになった。どこまでも作りものを作らないで進んでゆく、その溌剌たる生活こそ真実なものである。」
このような述懐から、剛毅木訥の五高生との交渉が、澤木の人生の重要な転機になったことが伝わってくる。
「彼らに出逢わなかったら、ついに既成宗教的な一線を脱することができずに終わったかもしれない」と言っている。
大慈寺には数年間滞在した。やがてそこを出て、熊本市内の借家で参禅道場を一年間開いたが、ある奇特な人が、熊本駅裏の万日山の頂上にある別邸を使わせてくれることになり、そこの「居候」となった。以来、万日山を拠点に、各地に赴いて座禅の指導や説法をした。自然児五高生との交流によって開眼した澤木興道の、「移動僧堂」、あるいは「宿無し興道」と称された新たな人生の始まりであった。
森田療法は、禅思想には教えられるところが多い。しかし、禅の教条的で、かつ形式を重んじる面にはついて行き難いというジレンマもあるから、僧が民衆の中に入ってくる普段着のような禅には親和性を覚える。欲も金も持たない「宿なし興道」の禅に、虚飾のない生き生きした魅力を感じるのである。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
4.禅僧の戦争体験と思想 ―森田正馬と対比して―
ところで、考え直しておかねばならないことがある。上に記した澤木興道と五高生たちとの交流のエピソードを、父親のような世代の男が、息子のような学生たちと裸の付き合いをした痛快な話として、おしまいにすることができるだろうか。残念ながら、ここでめでたく話を閉じるわけにはいかない。
澤木は学生たちによって、素っ裸にされ、「兵隊以来、勉強と座禅で神経が細くなっていたわしも、見事に作り直された」と言うが、どんな「わし」がどのように作り直されたのであろうか。純粋無垢な五高生たちに、自分が日露戦争で体験した戦争の悲劇や罪悪を伝えただろうか。
万日山に長居をしていた澤木は、昭和10年に駒沢大学からの要請により、熊本に別れを告げて、同大学の教授となった。やがて軍靴の音が響き始めて、日本は侵略戦争に向かう時代のことである。五高の自然児たちの運命はどうなったのであろうか。駒沢大学の澤木は、軍事政権の近くに身を置くことを辞さなかった。
昭和10年代の澤木は、戦争について、いくつかの発言をしている。自分は、日露戦争で兵隊に行けば人殺しも名人の方であった、と言っている。しかしそれは、自分が生まれつき胆力があったからに過ぎず、座禅で胆力をつけたのではないと付け加える。この文脈で、座禅は仏行であるが、戦争は無間の業であり、仏行と戦争は反対のものとして、区別する見解を述べている。ところがその見解は一貫しない。驚くべきことに、戦場における殺戮を、仏教思想によって合法化しているいくつかの発言に遭遇する。少年の頃、やくざたちの斬り合いを見たというこの人の原体験が、つい重なって見えてしまう。任侠道と仏道と戦争が一緒になっているかのようである。とにかく悲しい話だ。
さて、森田療法の立場から禅に求めていることがある。それは禅語の断片や禅の難解な思想ではない。座禅の警策でもない。問題は禅者の生き方である。
澤木興道の後半生については、もはやここでは論じ尽くせない。稿を改めるほかなかろう。
一方、森田正馬の戦争に対する考え方はどうだったか。森田は反戦主義者だったという単純な捉え方をして、美化する風潮があるようである。果たしてそうか。森田は、与謝野晶子のように、反戦思想を詠嘆的に謳うことはしなかった。出征した弟、徳弥に対して、無駄に命を落とすなと言っただけでなく、敵前逃亡をするなとも諭しているのである。彼は弟に対して、「怯懦と匹夫の蛮勇とは、どちらも男子として最も賤しむべきものである」と教えた(野村章恒『森田正馬評伝』による)。戦場へ赴く肉親に対して、なんと厳しいことを言ったものかと思う。
森田は、暴力や戦争に賛成しているわけではないが、世の中の事実であり現象であると言って、それを受け入れている。
「戦争は世界に絶えない。事実であるから、善くとも悪くともしかたがない。兵法は、戦わずして勝つのが上乗であって、国には軍備が整って、外交で勝つのが、上策であろうと思う。」と述べている(第42回形外会)。同様のことを、第46回形外会でも、「読んで字の如き平和論や無戦論は社会人心の本然性を無視した屁理屈である。」と言い、武力を充実させて、「戦わずして勝つ」の平和を説いている。
戦争というものを、森田正馬はこのように捉えていた。彼は極めて現実主義的な思想の持ち主だったと思う。しかし、事実として戦争が起これば、澤木興道が体験したような事態に直面するわけである。
澤木の戦争体験と発言は、禅僧の戦争責任につながるが、弟を戦争でうしなった森田の思想は、森田療法とも絡んで、われわれに迫ってくるのである。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
〈主要文献〉
1) 澤木興道と五高生の交流に関するもの
・澤木興道 : 禅に生きる. 誠信書房. 昭和31年
・酒井得元 : 澤木興道 聞き書き. 講談社. 昭和59年
2) 澤木興道と戦争に関するもの
・澤木興道 : 證道歌を語る. 大法輪閣. 昭和15年
・ブライアン・アンドルー・ヴィクトリア : 禅と戦争. 光人社. 平成13年
・遠藤 誠 : 今のお寺に仏教はない. 現代書館. 平成7年
・市川白弦 : 仏教者の戦争責任. 春秋社. 昭和45年
・松岡由香子 : 「禅と戦争責任」-沢木興道老師のアポロギア. ネット上の文献(掲載誌不明. 未出版原稿か?)
・松岡由香子 : 「禅と戦争責任」(続き)-沢木興道老師のアポロギア. 第二部 禅と戦争. ネット上の文献(掲載誌不明. 未出版原稿か?)
・澤木興道 : 生死のあきらめ方.
・澤木興道全集. 大法輪閣.
3) 森田正馬の戦争に対する考え方
・森田正馬全集 第五巻. 白揚社.
・野村章恒 : 森田正馬評伝. 白揚社.
2017/08/29
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
森田正馬が、自分の療法は人間の再教育であると言い、療法の教育的な面を重んじていたことはよく知られている。森田はモンテッソーリの幼児教育や、藤村トヨ女史が行っていた体育など、教育に広く関心を寄せていたのであった。そして何よりも自宅に患者を入院させて、本物の夫婦喧嘩まで公開しながら、自分たちの家庭を教育の場として、実際に即した指導をおこなった。このような家庭教育的な療法を身をもって体験し、それを継承していた水谷啓二の森田療法と、下村湖人や永杉喜輔の社会教育が合流することになる。家庭教育と社会教育は、別物ではない。これらが相互補完的になって教育が充実する。
♥ ♥ ♥
そこで、唐突かもしれないが、高知出身の森田正馬が創案した療法と、下村、永杉ら、九州の五高出身者たちに発した社会教育の流れとの関係を、精神的風土の面から考えてみる。水谷啓二の著書、『あるがままに生きる』(昭和46年刊)の中に「もっこすといごっそ」という見出しの注目すべき一文があるので、それを取り上げておきたい。
水谷は、高知県在住の精神科医、沢田淳氏から『いごっそう考』という本を贈られたので、読んでみて、興味深く感じたというのである。沢田淳という人は、慈恵医大卒の精神科医で、高良武久教授の弟子にあたり、郷里の高知県に帰って、浪越診療所で森田療法の開業をしていた人物である。森田正馬は高知県出身だったし、水谷啓二は熊本県の出身者だった。だから森田は「いごっそう」で、水谷は「もっこす」であったと即断するのはさておいて、水谷は沢田の著書に対して、感想を述べているので、次にそれを要約して紹介する。
―― 沢田氏は言っている。〈いごっそう〉は明朗闊達であるが、ときに重大事に出くわせば、他人の毀誉褒貶に重きを置かず、不変の信念をもって、正義に向かってまっしぐらに生命をかける、と。そのように、むしろへそ曲がりとも言えるほどの頑固さで、自分の信念を貫こうとするところは、肥後のもっこすも同じではないだろうか。それが極端になれば、〈偏屈〉となって厄介視されるけれども、豊かな人間味と高い知性とに裏づけられていれば、不撓不屈の精神をもって、創造的な事業を成し遂げてゆく底力ともなるであろう。現代の文化の中に感じられる欺瞞性を看破して、日本古来の純粋な精神に根ざした、新しい創造的な文化を開拓していくのは、「もっこす」的あるいは「いごっそう」的な人たちではあるまいか。――
以上が、水谷啓二自身の感想の概要である。ちなみに著書『あるがままに生きる』は、昭和45年に急逝するまで、水谷が熊本日日新聞に「宗教随想」として連載していた原稿が集められ、病没の翌46年に出版されたものである。八面六臂の活躍をしながら、森田の生活道をまっしぐらに生きて逝った水谷氏自身、氏の一文に照らせば、よき「もっこす」だったと言えるであろう。
♥ ♥ ♥
それにしても、人はさまざまであり、伝説的な県民性で安易に人を見るのは慎まねばならないのだが、精神的風土によって形成される人の気風の特色は、なきにしもあらずであると思う。
水谷と五高での同級生で、下村湖人に師事して、社会教育に貢献した永杉喜輔(群馬大学教授、のちに名誉教授)もまた、熊本県出身者である。永杉は京大の哲学科に学んで、観念的な哲学用語を振り回していた青年だったが、卒業後、小金井の浴恩館で、五高の先輩であった下村が主宰する青年団の講習生活に加わり、便所掃除をしている下村の姿を見て、開眼したのだった。以後、あまり日の当たらない社会教育の道を、熱意を持って駆け続けたのである。永杉も「もっこす」と称されてよい人物であった。
♥ ♥ ♥
ところで、下村湖人は九州男児であるが、熊本ではなく佐賀県の出身である。もともと彼は、文学肌でロマンチストの若者であった。中学生のときに、既に中央で頭角を表し、その名を世に知られていた天才詩人であった。しかし早熟な下村の神経は繊細であった。孤独な思索の中に入りがちな彼であったが、五高時代に同じ佐賀県人である2人のよき友人に恵まれた。彼らとの心の交流によって、高校時代の下村は人間的に成長していった。
ひとりは、佐賀中学で同窓だった高田保馬である。高田は、後に京大に進み社会学を専攻して京大教授(のちに名誉教授)になった人物である。五高時代の下村にとって、高田は胸襟を開いて付き合うことのできた無二の親友であった。二人は、共に校友会誌「龍南」の編集委員になり、また寮では同室であった。二人は、時には同じ布団にくるまって寝た。しかし、高田はやがて病気で休学したので、生活を共にすることはできなくなる。それでも二人の友情は長く続き、互いに生涯を通じての友となった。小金井市の(旧)浴恩館には、青年団講習所所長時代に高田が訪れて、両人が一緒におさまった写真が残されている。
♥ ♥ ♥
もうひとりの友人は、これまた佐賀県出身の田澤義鋪(よしはる)である。田澤は、下村より先に五高に入学した一年上の先輩であったが、ボート部の選手で、学校の禁酒令を破って酒を飲み、退学となった。その後復学を認められ、一学年遅れて下村と同学年となったために、以後身近な関係になったのである。文武両道に長け、正義感が強くて豪胆な田澤に、自分にないものを見て下村は心酔した。田澤も、詩人としての下村の天賦の才と、葉隠のように秘めたその武士的な気質に敬意を払っていた。田澤は東大の法科に進み、卒業後に官吏になるが、官界の枠にはまらず、国内の青年たちに対する教育の必要性を感じ、青年団運動の指導者となった。下村は同じく東大を出たが、一旦郷里の佐賀県や台湾での教員生活を経験してから、田澤の世話で青年団講習所の所長を引き受けることになった。こうして田澤と下村の二人は、五高以来の歳月を経て、志を共有し、青年たちへの社会教育を共に推進することなった。
田澤から受けた鼓吹なくして、下村の人生を賭けた社会教育活動はなかったであろう。葉隠のように、耐え忍んで活動する武士道的な気質は、下村において顕著であった。一方、剛毅で、尚武の気性に富む田澤もまた武士のようであったが、彼の剛毅な気質は、肥後「もっこす」にも通じるものであったと言えよう。
♥ ♥ ♥
肥前(佐賀)の気風は俗には「いひゅうもん(異風者)」と言い、尚武の気性を有し、剛毅朴訥、一徹で、角が立ち、融通がきかず、協調性に欠け、保守的などの気質特徴を指すらしい(高松光彦『九州の精神的風土』より)。「いごっそう」や「もっこす」と反対であるような印象を受けるけれども、同じものを裏面から見た特徴のようでもある。
ともあれ、「いごっそう」、「もっこす」、そして「葉隠の精神、もしくは、いひゅうもん」は、根底にある共通する気風の上に、若干のスペクトラムの差を見ているのではなかろうか。
日本の社会教育を開拓した人材が、こぞって熊本五高から輩出しているので、その背景にあるかもしれない九州人の精神的気質について、少し考えてみた。五高が生んだ社会教育者たち、田澤義鋪、下村湖人、永杉喜輔、さらに水谷啓二といった人物の列伝については、改めて触れたい。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
2017/08/14
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
森田正馬は、昭和13年に60歳過ぎで没している。下村湖人は、ちょうどその頃、昭和8年から昭和12年までの間、武蔵小金井の「浴恩館」(日本青年館の分館)に付設された「青年団講習所」の所長として、集団合宿に集まった青年たちと起居を共にしていたのだった。その塾風生活における指導は、あたかも入院森田療法のようである。しかし森田と下村との間に交流があったわけではない。
下村は森田と同じく熊本五高の出身者である。森田より10歳年下で、五高は森田の8年後に卒業して、東大英文科に進んでいる。
二人の間に出会いが起こることはなかったが、下村の社会教育の活動は、弟子の永杉喜輔を通じて、やがて水谷啓二の森田療法に合流することになる。永杉と水谷は熊本五高の同級生であった。永杉は五高から京大の哲学科に進んだ後、浴恩館における下村の青年団講習所に学び、以後下村に師事し続けた。水谷は五高から東大の経済学部に入り、卒業後はジャーナリストになっていた。戦後に社会教育の立て直しを図ろうとする下村のもとにいた永杉は、かつての同級生の水谷と再会し、彼を下村に紹介した。こうして、下村が拓こうとする社会教育と、森田の生活道を追求していた水谷の活動が、軌を一にすることになるのである。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
野口周一先生は、下村湖人や永杉喜輔らについての研究者であり、社会教育の実践者でもあるお方である。かつて下村が、戦後に創刊した社会教育のための雑誌、「新風土」は消滅し、行き着くところ、水谷啓二の雑誌「生活の発見」に、「新風土」の誓願を委ねるに至ったが、野口先生はその流れを追って、森田療法や「生活の発見会」に到達された。私はと言えば、森田療法における自助組織に関心を持って、「生活の発見会」のルーツを辿ったら、永杉喜輔に、そして下村湖人に遭遇することになった。こうして野口周一先生とのご縁ができたのである。
去る6月の下旬、私は上京した折に小金井市の(旧)浴恩館を訪れた。関東在住の野口先生は、このとき親切にも、私の日程に合わせて浴恩館公園においでくださり、さらに公園の近くにお住まいになっている下村湖人の縁戚のお方をご紹介くださったのだった。縁戚のお方は、浴恩館公園美化サポーターとして、ボランティアで公園の美化に尽くしておられる中嶋直子様である。三人で公園に行き、野口先生と中嶋様に丁寧に説明していただきながら、(旧)浴恩館の館内や公園の敷地内を見学することができた。
この浴恩館公園は、小金井市が所有しており、(旧)浴恩館の建物は、小金井市文化財センターになって、市内の考古資料などと共に、浴恩館だったときの資料や下村湖人に関するものが多く展示されている。青年団講習所で共同生活をしている青年たちの写真や、剣道の道場の写真も展示されていて、当時の研修生活が視覚的に伝わってくる。学術用に展示物の写真撮影を許可されたが、そのような写真は、残念ながらブログに出すことはできない。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
講師用宿舎として、空林荘という、こじんまりした瀟洒な建物があった。下村湖人がここに住まい、『次郎物語』の執筆の想を練り、第一部を書いた場所である。
空林荘は、貴重な建物として、市の史跡に指定されていたが、平成25年3月に焼失した。
市史跡 空林荘
この空林荘は、全国の青年団活動の中心であった財団法人日本青年館が、昭和5年にその分館として浴恩館(青年団講習所)を開設したとき、講師の宿舎として建てられたものです。
青年教育の実践家として知られる下村湖人(1884~1955)は、昭和8年から同12年まで講習所の所長を務めました。 空林荘は下村湖人が講習生と寝食を共にし、指導にあたったところです。
そのころ、「次郎物語」の執筆を始めた湖人はここで構想を練り、次郎の少年時代を記述しました。昭和29年に発表された第5部に登場する友愛塾と空林庵は、浴恩館と空林荘をモデルにしたものです。
なお、空林荘は貴重な文学遺跡として市史跡に指定されましたが、平成25年3月に焼失しました。
平成26年3月
小金井市教育委員会
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
「大いなる 道といふもの 世にありと 思ふこころは いまだも消えず」
歌碑には、下村の書いた字体が、そのまま拡大されて刻まれているようだが、判読するのが難しい。刻まれているのは、上記の歌である。
下村は戦前とほとんど変わることのない「新風土」の誓願を掲げていた。その一部を拾えば―、「個性の自律的前進が、同時に調和と統一への前進であり、全一なるものの歓びであるように行動したい。」、「伝統にはぐくまれ、歴史を呼吸しつつ、しかも生生発展(…)、新しき歴史と伝統とを創造したい。」と謳われている。
しかし、伝統の上に個人の自律を模索する誓願にのっとって発行した雑誌「新風土」は、戦後の社会にあまり受け入れられることなく、廃刊のやむなきに至った。永杉によれば、下村は「甘かった」と嘆息したと言う。
それでも、浴恩館での塾風生活体験を描いた『次郎物語 第五部』が、昭和29年4月に出版の運びとなった。
その秋、昭和29年10月3日、古希の誕生日に、下村は「大いなる道…」の歌を詠んで、新たな前進を自身に誓ったが、その肉体は既に病に蝕まれており、翌年4月に世を去ったのだった。
2017/07/30
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
1. 森田正馬の参禅
森田正馬は、形外会の席で、自分の禅体験を述べている。
「釈宗活師の提唱を聴き、また参禅もした。そのときに『父母未生以前、自己本来の面目如何』という公案をもらった。三度参禅したけれども、公案を通過することができなかった」、「ただ物好きの野次馬にやっただけの事である」などと言っているのである。しかも、このような挫折体験のために、「私は禅のことは知らない」とか、自分の療法は「全く禅とは関係がない」と言い出す始末となった。
森田の参禅については、彼の時代に文化人はよく鎌倉の円覚寺の釈宗演のもとに参禅したので、釈宗活という名が釈宗演と混同されて、結局森田の参禅についての正確な事実は、今日までほとんど不明のままであった。しかし、森田の日記を見ても、明治43年に谷中初音町の「両忘会」の釈宗活老師に参禅したと、明記されている。そこまでは疑いを入れないことである。
では、森田が通った「両忘会」とは、どんな禅道場だったのか、そして釈宗活老師とはどんな人物だったのであろうか。
昨年12月から今年の2月頃まで、森田の参禅体験の事実を明らかにするべく、調べを続けながら、判明したことを順を追って、詳細なレポートを本欄に連載し続けた。
調べる中で、かつて釈宗活老師を師家と仰いでいた「両忘会」の流れがあり、それを受け継いでいる「擇木(たくぼく)道場」が、谷中7丁目に現存することを知った。しかし「両忘会」や釈宗活老師について不明な点があり、その道場に連絡を取って質問を向け、責任者の師家、杉山呼龍先生から回答を頂いた。
しかし、そのときは通信によるやり取りのみで、擇木道場をお訪ねできずにいたのだった。遅ればせながらその失礼を謝し、また「両忘会」の歴史や釈宗活老師の人物像について、さらに教えて頂ければと、去る6月下旬に擇木道場をお訪ねした。
先の連載の際に既に明らかにできたことは、本稿では重複を避け、新たに教えて頂いたことや、擇木道場を初めて訪問した体験を、少し記しておきたい。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
2. 両忘会、擇木道場、そして人間禅へ
擇木道場は、山手線の日暮里駅の最寄りで、谷中の墓地と天王寺という天台宗の寺院との間に位置している。
道場をお訪ねしたら、師家の杉山呼龍先生が快くお迎えくださった。この杉山先生と対座してお話しを伺うことができ、両忘会の歴史や釈宗活老師のことについて、種々教えて頂いた。
明治43年に森田正馬が、師家の釈宗活老師のもとに参禅した「両忘会」は、谷中初音町(旧町名)にあった。しかし大正3年に谷中天王寺町(旧町名)に新築の建物を得て、「両忘会」はここに移転した。そして道場名を擇木(たくぼく)道場と称するようになった。それが現存するこの擇木道場の由来である。
当時は、なお「両忘会」であったが、その後大正末に財団法人「両忘協会」、また昭和12年には宗教団体「両忘禅協会」と組織変えをして、本部は千葉県市川市の新道場に移された。これにより、擇木道場は学生の寮になっていた時期がある。昭和24年に千葉の組織は、宗教法人「人間禅」となって、全国に支部を増やし、在家禅の振興がはかられて、今日に至る。この在家者による「人間禅」が始められるまでは、釈宗活老師は千葉において、両忘禅協会の師家として参禅者の指導を続けておられた。
擇木道場は、千葉の本部に「人間禅」が成立してから後に、「人間禅東京支部」を名乗ることとなった。ともあれ擇木道場は、かつて釈宗活老師によって長年にわたり在家者の禅指導が行われた由緒ある道場である。
要するに、森田正馬が参禅した「両忘会」なるものは、在家禅(居士禅)として戦後に独立組織となった「人間禅」の前身で、禅の老師を指導者と仰ぎ、在家者たちが集って参禅していた、禅組織だったのである。
最初期の「両忘会」は、山岡鉄舟、中江兆民らの有志により、寺院の殻を破り在家禅を振興しようと、明治8年に湯島の麟祥院で、鎌倉から今川洪川老師を招いて、禅を学ぶ会が開かれたのだった。しかし、洪川が辞したために会は途絶えていた。
その後、釈宗演の命により、釈宗活が明治34年に「両忘会」を再興したのである。その頃の道場は、借家を利用して、根岸、日暮里、谷中を点々と移転したようだった。先立っての本欄の連載に記したが、森田正馬が参禅した明治43年の時点の「両忘会」の場所は、谷中初音町(旧町名)二丁目であったと推測された。だが、その環境はよくわからない。森田が「両忘会」の場をどのように捉えていたか、また釈宗活老師にどのような印象を抱いたのか。自身にとって重要な体験だったに違いないのに、公案を透過しなかったことだけをポツリと言い、「両忘会」や釈宗活老師との出会いの体験について何も述べていないのは、なぜだろうか。そのへんに不思議なものが残る。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
3. 在家禅(居士禅)の指導者、釈宗活老師
釈宗活の名は、釈宗演の陰に隠れて、あまり知られず、またしばしば混同されている。だが、その人柄と、人を引きつける禅の提唱、さらに絵画、鎌倉彫りの彫刻や三味線などの多彩な芸道に秀でていたことでも、玄人受けする人だったようである。若き日に宗活老師を慕って擇木道場に住み込んで座禅をしたという西山松之助氏は、自著に、浄土真宗の近角常観と禅の釈宗活は、明治・大正を代表する二大宗教家だと言われた、とまで書いている。
夏目漱石は、円覚寺の釈宗演のもとに参禅した体験を、小説『門』にかなり詳しく書いている。宗活は宗演から塔頭の帰源院の監理を委ねられ、外部から参禅に来る人たちを宿泊させて、その世話にあたることになった。漱石の参禅はこの頃のことで、『門』では、宗活は宜道という名の若い僧侶として描かれている。
「紹介状を貰うときに東京で聞いたところによると、この宜道という坊さんは、大変性質のいい男で、今では修業も大分出来上がっているという話だった…」、
「この矮小な若僧は、まだ出家をしない前、ただの俗人としてここへ修業に来た時、七日の間結跏したぎり少しも動かなかったのである。」、
「この庵を預かるようになってから、もう二年になるが、まだ本式に床を延べて、楽に足を延ばして寝たことはないと言った。冬でも着物のまま壁にもたれて坐睡するだけだと言った。」
一方、漱石の『談話』の中の「色気を去れよ」という題の話の中では、宗活の剽軽な面が語られている。
「明治二十六年の猫も軒端に恋する春頃であった。私も色気が出て態々相州鎌倉の円覚寺まで出掛けたことがあるよ。(…)。
如何なる機縁か、典座寮の宗活といふ僧と仲好しになって、老婆親切に色々教えて貰った。(…)。
其の夜宗活さんが遊びに来て、面白いものを聞かしてくれた。白隠和尚の『大道ちょぼくれ』で、大に振っている。宗活さんは口を尖らしていふ。
〔中略〕(ママ)
宗活さんは剽軽な坊さんだと思った。」
さらに漱石は、参禅を回想し、「禅僧宗活に対す 一句」として、次の俳句をよんでいる。
「其許は案山子に似たる和尚かな」
意味を判じ難い句である。
このような漱石の描写は、参禅体験者の目から見た釈宗活像である。
かなり以前の、両忘禅協会の時代に、釈宗活老師が自叙伝を語られたことがあり、その記録が当時の会報に掲載された。間接資料でそれに接することができた。それによると、釈宗活は、東京麹町の開業医の四男として生まれた。本名は、入沢譲四郎であった。11歳のときに母が早逝したが、臨終のときに「よく聞けよ。母は御身の富貴栄達を望まぬ。心を磨け」と言い残した。引き続き翌年に父も他界した。以後、少年は母の遺言を守って、苦学し、ストイックに生きた。今北洪川について円覚寺に入り、出家したが、一生寺の住職にはならず、在家者に禅を伝えることをおのれの使命としたのだった。
森田正馬はこのような禅僧との貴重な出会いに恵まれながら、参禅の途中で挫折してみずから去った。
惜しむらくは、在家者の森田が、在家者への禅指導を一筋とする、願ってもない人、釈宗活老師に巡り会いながら、その縁に反して、この老師に師事できる貴重な機会を逸してしまったのである。
ことによると、森田は後にそれを悔やんで臍を噛んだのではなかったろうか。だから、禅について自己を卑下する言葉が、口をついて出たのではなかったろうか。ちなみに森田は、後年に釈宗活老師の禅の著書を買って読んでいるのである。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
4. 擇木道場の現在
谷中界隈には、古い東京の風情が残っている。昇ったり降ったりと、坂が多い。山手と下町の重なりあった雰囲気がある。山岡鉄舟が開いた全生庵も谷中にあって、安倍総理が座禅をしに行くことでも知られている。天王寺には、幸田露伴の小説のモデルになった五重塔があったが、焼失してしまって今はない。江戸時代には、このお寺で、幕府公認の富籤の興行が行われていたらしい。
さて、その天王寺のそばにある擇木道場にお邪魔した。大正4年に、両忘会のために道場を新築寄進されたものだが、老朽化により、平成になって建物は改築されたようである。
道場の責任者の師家、杉山呼龍先生(仰月庵杉山呼龍老居士)は、温厚な御方であった。人間禅や擇木道場の沿革、釈宗活老師のことなど、親切に教えて下さった。道場内部も見学させて頂いた。寺院で感じる、あの独特の雰囲気がないのがいい。京都では、禅と言えば禅寺、そして禅寺と言えば、連想は座禅か観光かの二択となる。二択どころか、座禅と観光の両目的で、京都にやって来る人たちもいるから、かなわない。
人間禅の擇木道場は、当然ながら禅寺の雰囲気に包まれていないし、観光とも無縁である。それだけで十分に無駄がなく、したがって禅の本質が問われることだろうと思う。日常生活との間に敷居のない、そんな禅道場を初めて見学させて頂くことができて、大変印象深かった。
杉山呼龍先生のほかに、もうお一方、笠倉玉渓先生(慧日庵笠倉玉渓老禅子)にも、お目にかかることができた。禅の知識と経験に富んでおられる上、聡明で気品のある女性の指導者でいらっしゃる。笠倉先生は、人間禅の特命布教師に任命されて、各地で講演をなさっている。また、「禅フロンティア 日本文化研修道場」(本部は、擇木道場)の代表もつとめておられる。
擇木道場では、摂心会をはじめ、座禅会、勉強会、講演会など、さまざまな行事が開催されている。音楽のライブと座禅が、コラボでおこなわれたこともある。
「人間禅 擇木(たくぼく)道場」のホームページを開けば、さまざまな情報が満載されている。
講演の動画も多い。
2015年は、擇木道場創建100周年にあたり、記念勉強会として、笠倉先生や杉山先生がなさった講演を、今も動画で視聴することができる。
杉山先生の講演は、在家禅の発生と歴史についての、貴重な研究的内容の講演である。
笠倉先生の講演は、基調として、現代人の生活の中に禅をどう生かせばよいか、をわかりやすく語っておられるものである。森田療法家が学ぶべき語り口にて、つくづく教えられる。
このような動画(いずれも Youtube)を、以下に列挙しておく。キーワードだけでも容易にアクセスできるので、是非視聴されたい。
1. 人間禅 擇木道場 100周年記念勉強会
・第1回 「大乗仏教とは何か?」
講師 慧日庵笠倉玉渓老禅子
(2015年10月10日)
・第2回 「在家禅の発生」
講師 仰月庵杉山呼龍老居士
(2015年11月21日)
2. 「心がブレない生き方と禅」シリーズ
・「心がブレない生き方と禅3~ストレス、負のスパイラルからの脱出~」
講師 慧日庵笠倉玉渓老禅子
(2017年4月5日)
この講演のみリンクをつけておきます
心がブレない生き方と禅3
その他いくつも、役立つ動画がある。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
後記:本稿は、2016年12月8日から2017年2月17日にかけてブログ欄に連載した記事、「森田正馬は鎌倉円覚寺に参禅したか」の続編である。また本稿の内容は、(第4章を除き)「研究ノート」に相当するので、「研究ノート」欄にも掲載する。これらの内容は別途に発表を予定しており、ここでは発表に先立ち、ルポルタージュ風に紹介した。
2017/07/24
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
残っていた宇佐玄雄の講話音声を、部分的に抜粋して、先に6月11日、7月8日、7月10日のブログ上で聴いて頂けるようにしました。森田正馬が改まって還暦記念講演をレコードに吹き込んだのと違って、日常の講話を録音したものなので、不自然さがありません。概してわかりやすく話しておられますが、早口で、一部には難解なことを言っておられますし、説明不足だと思われる箇所もあります。そこで内容や用語などについて、解説的に若干の説明を加えておきます。
♥ ♥ ♥
抜粋の小見出しでいうと、まず「あるがまま」は森田療法の基本的な教えであり、「そのまま前進」、「煩悩即菩提」のあたりは禅的立場からの指導で、森田正馬も、自分の言葉で「煩悶即解脱」と言い換えて指導している通りです。
♥ ♥ ♥
「森田先生の教え」の箇所については、今日の治療者はこのようには言いにくいのが現実です。いわゆるパターナリズム(父権主義)的な療法の面が極端に出ていますから。森田先生は仏頂面をして話も聴いてくれない、と日記に書いた人に対して森田先生が言ったことについてのコメントがあります。これは「あるがまま」のはき違えを指摘していると同時に、あたかも禅における師弟関係のように、患者は治療者の権威に従わねばならぬと教えているように受け取れます。本来は、治療者から滲み出るものに対して、自然に敬意の念が湧くような関係ができるのが望ましいのではないでしょうか。パターナリズム的関係の遵守をこう単純に言語化している講話を聴くと、私(ども)としても隔世の感を覚えてしまいます。そうは言っても、パターナリズムを抜き去ったら、森田療法は骨抜きになってしまうと私は思っているものです。
♥ ♥ ♥
「健康について」や「植物神経」のところでは、体のどこかの不具合に注意を向けると、感覚が鋭化し、悪循環が起こってしまうという、いわゆる精神交互作用について述べています。
他に健康に関しては、音声を抜粋できませんでしたが、“ A sound mind in a sound body “―「健全なる身体に健全なる精神宿る」と訳されている―の諺にふれておられる箇所がありました。そこでは、精神を健康にするためには、まず体を健康にしなければならないという論法で考えがちな誤りを指摘しています。この句は、元は古代ローマの詩人、ユウェナリウスが言ったもので、その原意は深いようです。まあ、それはともかく、玄雄先生は、sound という英単語を、healthy と無頓着に言っておられて、ご愛嬌です。先の植物神経の項の後半では、卑近な例を出しておられて、伊賀出身の忍たま先生の面目躍如としています。面白いので、聴衆はゲラゲラ笑っています。このような例を出されると、分かりやすいのでしょう。こちらは倫理コードを気にして、“(卑近な例も)”と書き加えていたのを一旦削除しました。しかし、多分大丈夫にて削除した言葉を戻します。
♥ ♥ ♥
「精神の対比現象」は、生と死、自と他、苦と楽などの分別のない一如の教えです。
「カンチャクを嫌う」という言葉も話の端にあって、説明を要します。これは『信心銘』の冒頭にある次の文中の一部です。
「至道難きこと無し、唯だ揀擇を嫌う」。ここに言う「揀擇」とは、より好みをすることで、読み方はいくつかあって、「ケンジャク」、あるいは「ケンタク」、あるいは「カンタク」と読まれます。玄雄先生は「カンタクを嫌う」と言ったのです。二分法でより好みをしてはいけない、という意味です。
以上はすべて禅の本領であり、森田が「苦楽超然」と教えたことと同じです。
♥ ♥ ♥
「うつすとも水は思はず うつるとも月は思はず 猿沢の池」。
この古歌は、柳生宗厳(石舟斎)が、一族に残した剣の極意歌だと言われています。猿沢の池は、奈良の興福寺のそばにあって、そこからさほど遠くない地に柳生の里があります。宮本武蔵を小説に描いた吉川英治氏も、この歌を愛でていました。
一方、「猿沢の池」でなく「広沢の池」となっている歌もあり、それは剣豪、塚原卜伝が詠んだ歌と伝えられています。いずれにせよ、剣の極意としての無心の境地を教えているものです。柳生流と奈良の猿沢の池にしておく方が風流なようですが、そもそも無心とは、風流、無風流の域のものではありますまい。
猿沢の池からの連想で、玄雄先生は、「手を叩く、云々」の歌も引用しておられます。間髪を入れずに、と教えていますが、少し説明を補います。
「手を打てば はいと答える 鳥逃げる 鯉は集まる 猿沢の池」という古歌があるのです。手を打って出す刺激音で、宿の女中さんはとっさに、はいと答えるし、鳥はたちどころに飛び立つし、魚は餌をもらえるかと集まってくるというのです。その心として、捉え方は相手によって千差万別であり、それぞれが思い思いに動くということを示しています。しかし玄雄先生は、この場合神経症者に対して、理屈抜きに即座に必要な行動をするようにと教えておられるのです。
♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
宇佐玄雄先生の言行のエピソードは、いろいろ知られていますが、不明な点も少なくありません。
講話でこんなことを言っておられたという、指導の言葉はいくつか語り継がれていますが、たまたま録音された講話中に、それらが展開されているわけではありません。でも今回は、音声や語り口にふれてもらうのが趣旨でしたので、講話の解説はこれくらいにしておきます。
これまで、こまごまと講話の音声をピックアップしてブログに上げました。通算すると30分くらいになるようです。
ホームページのファイルの容量に左右されますが、講話の全体をアップロードすることができるかもしれませんし、またCDに落として個別にお渡しできるかもしれません。
とりあえず、音声をピックアップしての提供とその解説は、これにて。