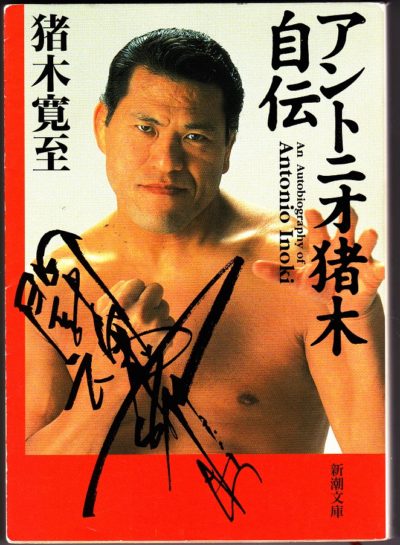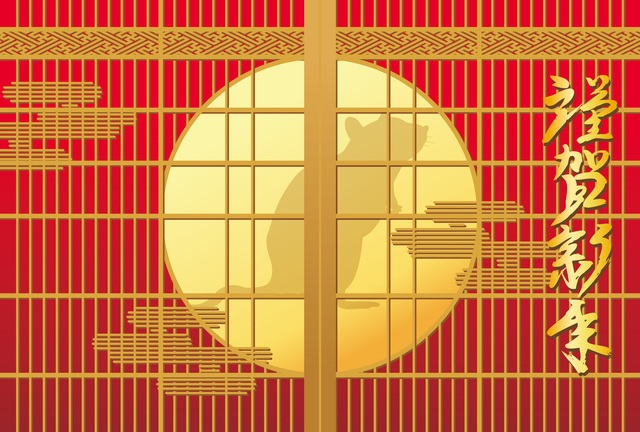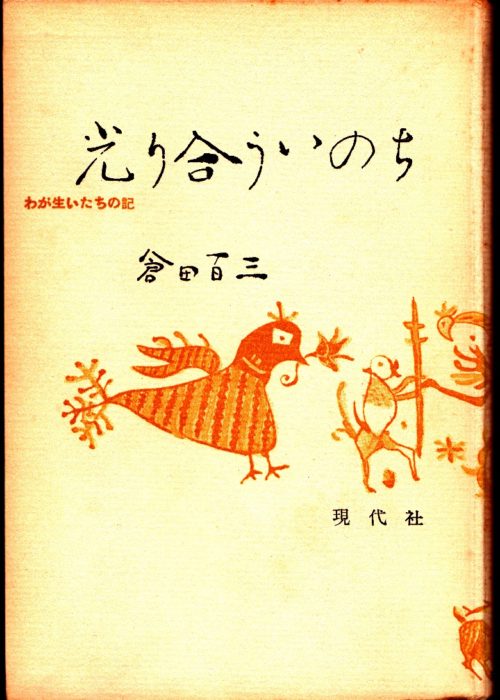♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
コロナ危機の時代の森田療法(中)
―森田療法は不要不急か?―
1. 森田療法に空白なし
2020年春、新型コロナウイルスの感染拡大により、三密の回避、不要不急の外出の自粛が要請された。神経症で受診を望んでいた患者さんらは、その間どうしていたのであろう。受診は不要不急に当たらないと考えて、通院を継続していたのであろうか。病院などにいけば、コロナウイルスに感染するリスクがある。そのため、一般に医療機関の外来受診者数は減ったと報道された。神経症を扱う診療部門ではどうなのか。
神経質や神経症は、症状にとらわれ、さらにそれを治すことにとらわれる病態である。つまり、「治したがり病」である。だからその「治したがり病」を治すことが大事であるにもかかわらず、昨今は森田療法を含めて、治療者も症状を治すことに同調している。緊急事態宣言が発令され、三密回避や外出自粛を強化する要請が出たことは、神経症者が通院をやめて、「治したがり病」を共有している治療者患者関係を断ち切る絶好の機会の到来を意味した。これを機に治療へのとらわれから脱却できた人たちは、どれほどおられるであろうか。気になるところである。
森田は曰わく、「休息は仕事の中止にあらず 仕事の転換にあり」と(注1)。 森田は状況に応じて仕事の切り換えをするところに休息があるのであって、中断の空白を要さないと言っているのである。コロナ禍で外出の自粛が要請され、場が在宅に移行しても、対応できる数々の課題があるはずである。
元高良興生院院長の阿部亨先生は、森田療法ビデオ(注2)の中で、「森田療法は人生の空白を作らない」ものだと力説しておられる。今日、想定外のコロナ危機のもと、医療、経済その他、あらゆるところで社会が揺さぶられている。森田療法はこのような事態とは無関係だと決め込んで、森田療法に不意にバカンス期が訪れたかのような錯覚を起こしているような方々は、まさかおられないだろうけれど。また学会やセミナーが開催され難くなったことが一大事だと嘆くならば、そこでも勘どころを外している。学会やセミナーも重要だが、本当の森田療法は生活の中にある。すべての現実や事実が真実である。コロナウイルスの影響を受けているわれわれの生活が、例外であるはずはない。
地球規模の危機のときに、行動が制約される条件下であろうとも、それぞれの人間が身辺から出発して、可能な方法で人とつながり、工夫し合えば、なすべきこと、できることを見つけ得るであろう。
森田療法は人生に空白を作らずに、密に生きる療法である。従って森田療法に不要不急という空白はあり得ない。
注1:
森田の言葉、「休息は仕事の中止にあらず 仕事の転換にあり」は、ヒルティの『幸福論』(第一部)に拠っている可能性がある。ヒルティは、本当の休息は活動のさなかで、働く喜びを感じるところにある、と言っている。森田においては、若干意味が変化しているが、この拙論では、休息についての森田の言葉の意味に忠実に従っている。
注2:
阿部亨『悩める人への生きるヒント』(野中剛監督)、森田療法ビデオ全集 第4巻、(有)ランドスケープ発売、2016

阿部亨『悩める人への生きるヒント』(DVD)のジャケット
2. 車間距離と人間(じんかん)距離
阿部亨先生は、同じく先のDVD『悩める人への生きるヒント』の中で、対人恐怖について述べ、人間関係には程よい距離が必要であることを指摘しておられる。若者は、人と距離のない関係が良い関係だと思い込み、その結果傷つけ合う体験をして対人恐怖になるが、ある程度の距離を保っている間柄が、社会的に健全な人間関係なのであると。ここで阿部先生は、中野翠という人が人間関係について書いていたことを紹介なさっている。中野翠という人はエッセイスト・コラムニストの女性であるが、「車に車間距離が必要であるように、人間同士にも車間距離のようなものが必要である」ということを書いているのだそうである。
中野翠さんは、長年「サンデー毎日」のコラムなどに機知に富む文章を書き続けてきた人である。件の文章の探索を試みたが、著書が多数あって、見つけることができなかった。ともかく、この人は、ご自身が、人間車間距離を意識して生きておられるのであろう。ペンネームの翠は、尾崎翠にあやかっているそうである。第七官界を彷徨なさっているのであろうか、本名やプライバシーを隠し、テレビ出演の依頼も一切断ってこられた。落語を愛するオタク系で、対人関係の機微に面白さを見ておられるのだろう。だから人間への興味が文章になる。この人は対人恐怖を楽しんで生きている、その完成型の人のようである。
人間において必要な「車間距離」とはよく言ったものであるが、これを「人間(じんかん)距離」と言い換えてもよいのではなかろうか。「人間」を「じんかん」と読むとき、それは世間、世の中を指す。東洋的な意味での社会である。市民の共同体である Society として社会を理解する以上に、「人間(じんかん)」として理解する社会は、物理的かつ心理的に距離ある人間同士のネットワークによって、それが成り立っていることがわかる。
ウイルス感染を避けるために、互いに2メートル程度の物理的な Social Distance を取るように要請されている。けれども、心理的な Social Distance というものもあるので、両者の関係はどうなのか。心理的には、知らない者同士が会話をする、いわゆる社会的距離はざっと2メートル前後とみなされている。物理的であれ、心理的であれ、社会的距離とされるものはいずれも2メートル程度で、ほぼ一致しているのである。さらに心理的には、個体の周囲の1メートル強より以内の同心円は、パーソナル・スペースと言われる個体の心理的安全圏になっている。人が1メートル強よりも近づくと、パーソナル・スペースが侵され、不快感が惹起され、親しい者以外はそのスペースに立ち入れない。つまり、本来人間は心理的に一定の段階の距離を置き合って生活しているのであって、その距離の中に、飛沫感染に対する防御域も含まれているのである。
コロナウイルスの感染を防ぐために殊更に言われた Social Distance は、都市生活における人間の異常な過密に対して発する必要のあるアラートであった。しかし、人間過密の都市環境を抜本的に変えることは困難である。あるいは、中野翠女史に学び、さらには対人恐怖の人たちに学ぶところが残されているのかも知れない。
対人恐怖と言えば、さらにその中に、通常の対人恐怖よりも、人と接近するのが一層苦手で、ふれあい恐怖と言われる一群がある。症状としては、会食恐怖や雑談恐怖などがあり、歓談しながら人に接近せねばならないという、和やかさが求められる状況が苦手な心理である。ひきこもり系に近いところがあるが、この心理は広く社会人一般にも見ることもできる。何かにつけ頻繁に飲み食いの集いをする日本人特有の宴会文化があり、これに適応する「お付き合い」を苦痛とする人たちがいる。ふれあい恐怖の周辺に広く位置づけられる心理である。社交性という柔軟さを欠くので、健全だとは言えないものの、Social Distance の観点からは、このようなふれあい恐怖系の方が正統派である。むしろ宴会依存症的な文化の方が問題である。ともかく神経症的な症状をすべて異常と決めつけず、秘められている意味を見直して、無理な矯正に走らず、折り合いをつけることが必要である。

3. 人間の新たな課題 ― ゴリラより、神経質に学ぶ ―
新型コロナウイルスが猖獗を極めつつある地球上のパンデミックの現象に対して、社会的文化的な立場から、多くの識者たちがコメントを発している。そのうち、去る5月にNHK・BS1で放送された番組「コロナ新時代への提言~変貌する人間・社会・倫理~」が、とくに注目された。
しかし、机上の学問を専門とする識者の提言というものは、えてして解説にとどまる。イタリアでコロナの死亡者が相継ぐ中で、遺体となってしまう死者への敬意が失われていると指摘したその国の哲学者が、疫学的認識を欠いていたというエピソードが哲学者から紹介されたが、むなしく聴いた。日本人は、志村けんが亡くなったとき、臨終に立ち会えず、遺体にも対面できなかったご遺族が、火葬後にはじめて受け取った遺骨を抱いておられる姿を見た。それですべてが伝わってきた。
人類学の立場からの山極寿一氏の発言を、期待して聴いた。山極氏の話は、前半では主に今日の危機状況が語られ、後半では人間社会の課題が示された。まず、山極氏の前半の話を、なるべく原文に忠実に、若干短縮して以下に紹介する。
「文明が始まる前から、人類という種は信頼できる仲間を増やすように進化してきた。文明の発達とともに人々は移動し、人と人の関係を作っていった。そのために人が集まること、移動するということが条件となる。そこで国が作られ、国と国が連携し、今、グローバルな社会が地球上に実現した。ところが、今それが崩されようとしている。新型コロナウイルスの出現によって、われわれは接触を禁じられ、移動を禁じられた。そのため、社会の作り方が根底から覆されてしまった。人が接触せず、移動せずに、このグローバルな社会をどのように運営するのか。それがわれわれに突きつけられた課題である。」
この前半部は、人間がグローバル化した社会を作ったという歴史の解説が主であった。一拍置いて、後半の発言を、多少要約しながら紹介する。
「ゴリラは、日々顔の見える距離で、体を合わせて互いが同調し合い、仲間であることを確認して、少人数でまとまっている。一方、人間は進化の過程で『離れ合う』ことを社会のひとつの条件として認めた。(人間は言葉を手に入れたために『離れ合う』ことが可能になったが)、言葉だけに依存してきたわけではない。言葉は進化の過程では、後で出てきたものであり、信頼を担保できるコミュニケーション手段ではない。むしろ、身体と身体が共鳴し合う中で、信頼が形成されてきた。ところが今、生身の肉体を通じた共鳴によるコミュニケーションが失われようとしている。言葉だけで繋がる世界に放り出されたとき、人間はどうなるのか。」
このように山極氏は問題を提起し、引き続き「人間は言葉の前に音楽を発明した。音楽は人と人との間を共鳴させる良い装置。」などとおっしゃった。そしてテレビ画面の半分には、楽器を抱えたミュージシャンの姿が映った。このような編集のパッチワークには、「間(ま)」というものがなくて、「間(ま)」が抜けている。ミュージシャンは、安倍総理のTwitterにコラボで出された青年であった。
音楽もいいけれど、生活し辛くなった日常生活に誰しも戻るほかない。最近、厚生労働省が「新しい生活様式」の実践例という資料を出した。行動の仕方が事細かに記されているが、これは神経質な人のそれとまるで同じである。病原性のウイルスはいつどこにでもいる。どのような生活様式がよいか、神経質者はほとんど無意識に知っている。みんなが神経質者の行動に学べばよいのである。ただし神経質者は、ときどき神経症のおかしな症状を出す。日本中でみんなが Social Distance に強迫的にこだわり症状を示しているのと同じである。お互いに症状は笑いぐさにしよう。そして、神経質者の持ち前の生き方に学ぼう。神経質を生きることは堅実であり、創造的である。『神経質礼賛』という著書を出し、「神経質礼賛」というブログを連載し続けておられる精神科医師がおられる(注3、注4)。大いに学ぶべし。
コロナウイルスは怖い。怖いままに気を配って行動するのである。
「随処に主と作(な)れば、立処皆真なり」(臨済義玄)。
注3:
南条幸弘 著 『神経質礼賛』白揚社、2011
注4:
ブログ「
神経質礼賛」(南条幸弘先生)
(下)に続く