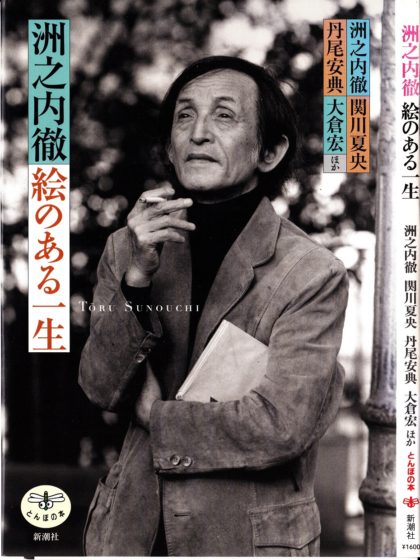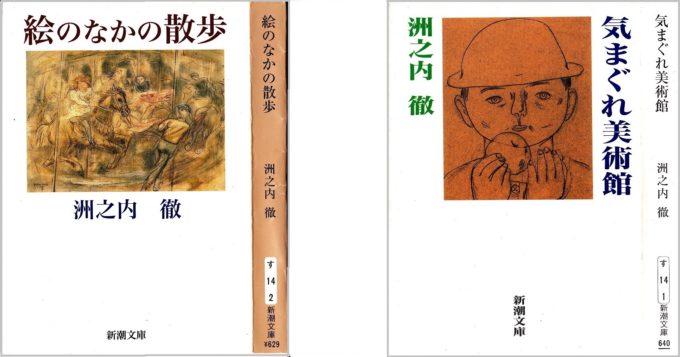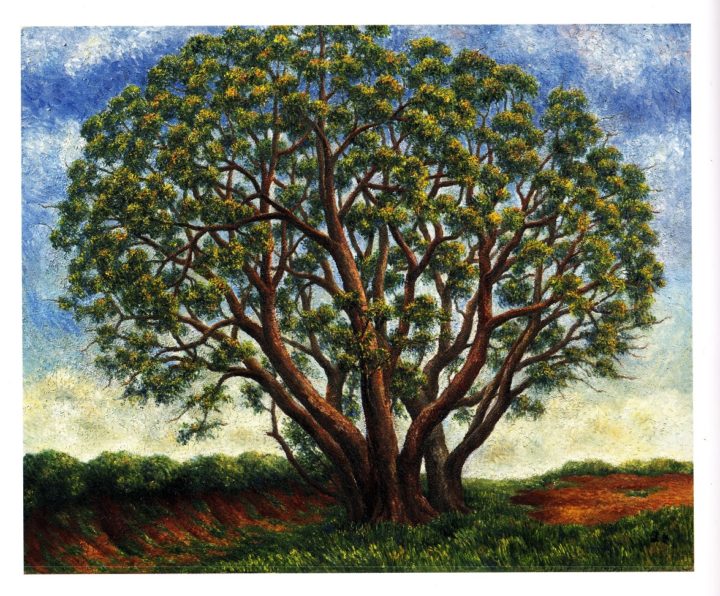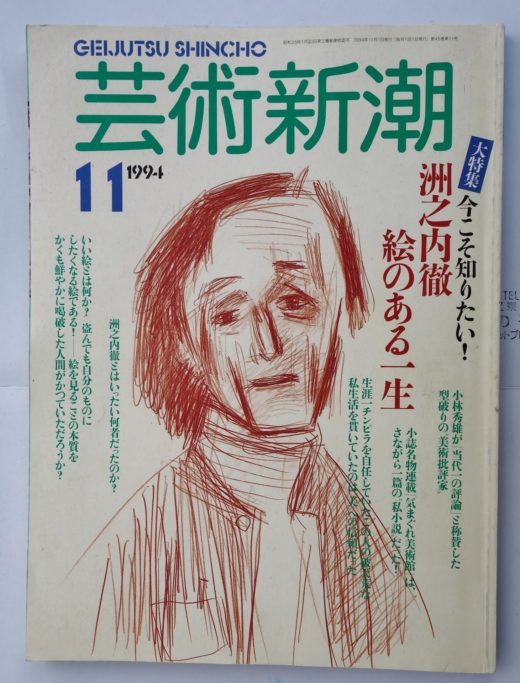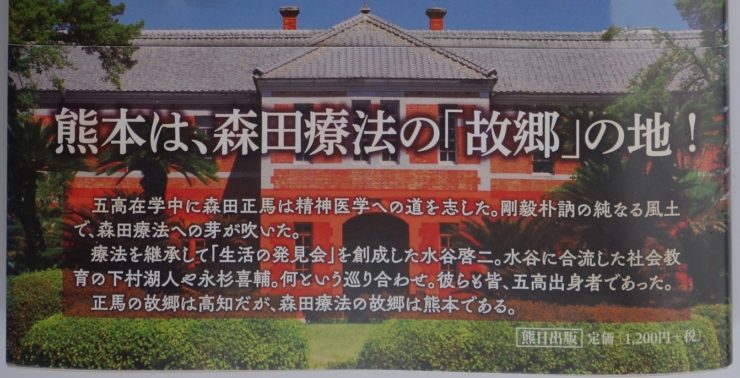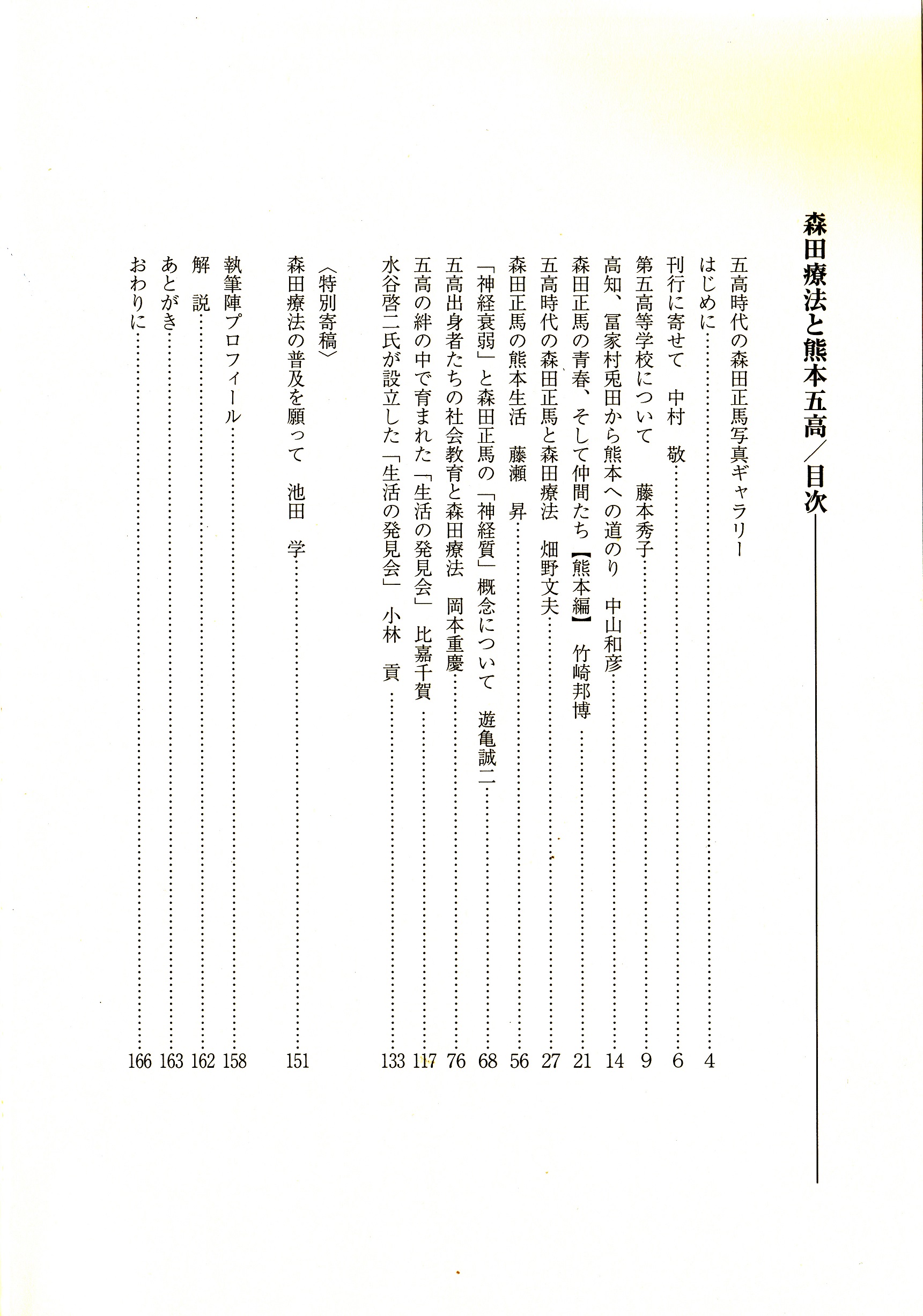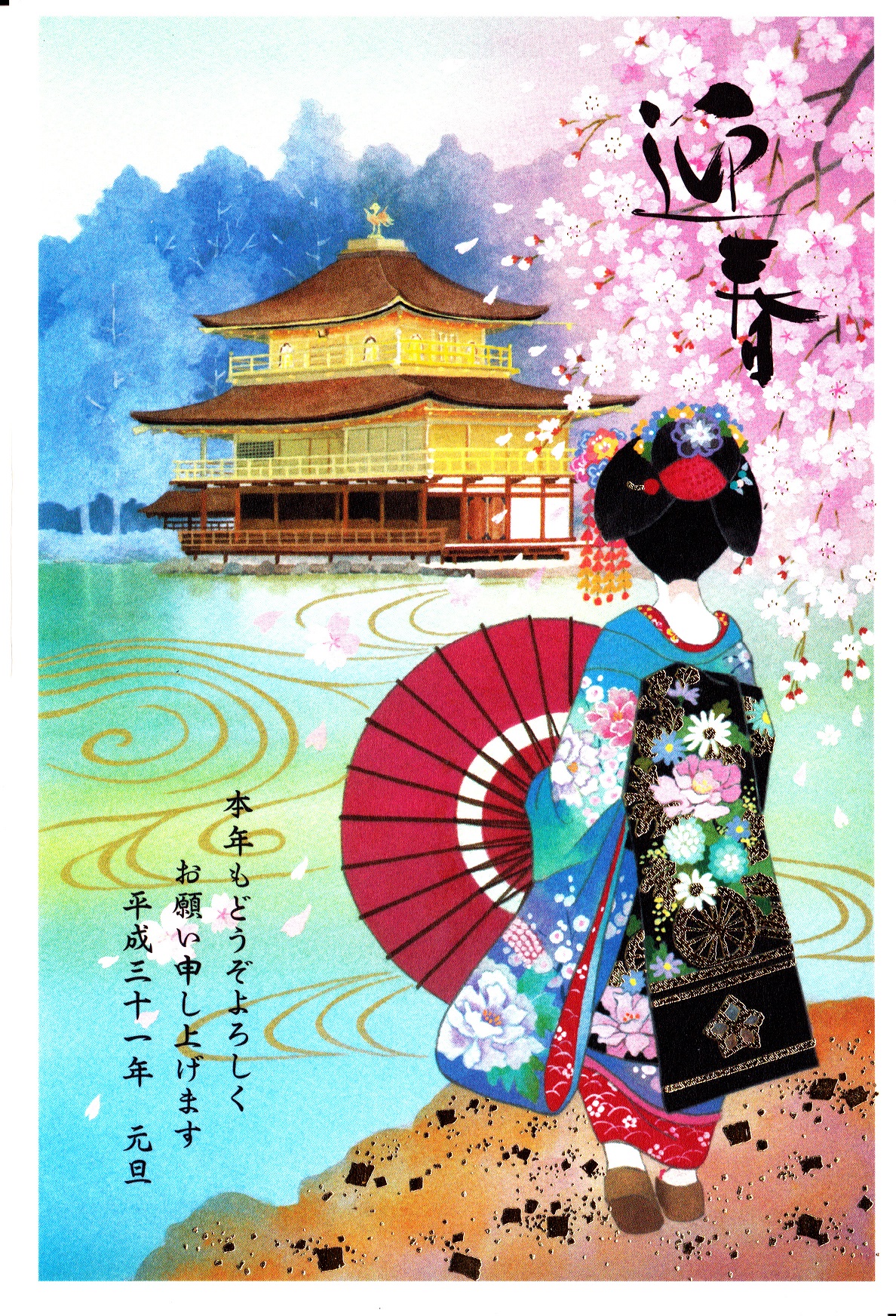2019年の今年は「森田療法創始百周年」か―森田療法考現学(5)― <その二>
2019/03/27

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
2019年の今年は「森田療法創始百年か」<その二>
(承前)
4. 「恐怖突入」と 「煩悶即解脱」
森田は、患者の精神交互作用を打破して、「煩悩即菩提」あるいは「煩悶即解脱」の体験に導くために、あえて人為的に指示を加え、有無を言わせず恐怖に突入させる方法を用いた。これがヅボアと異なる森田一流の「説得療法」であり、「体験療法」なのであった。ヅボアは体験よりも論理を用いて神経症者の病的心理を解消させようとしたのに対して、森田は体験に重きを置き、患者に説得的に具体的方法を授けて、恐怖に直面させた。
「恐怖破壊法」とも言い、行動療法におけるフラッディングと似ているが、「煩悶即解脱」に導くものである点で、やはり非なるものであった。したがって、森田が「体験療法」と言う場合、方法的に二重の意味があった。通院療法の段階で開発工夫していた「恐怖破壊法」と、もうひとつはもちろん、入院のとりわけ第一期の絶対臥褥において、恐怖と一体化せざるをえない体験を指していたことは言うまでもない。時系列的には前者(恐怖破壊法)が先行し、続いて入院による方法として後者ができた。
前者、つまり相手に見合った教示を用いて「恐怖突入」をさせる方法も、症状を治すにはそれなりに手応えはあったようで、森田は入院療法を始めてからも「恐怖破壊法」を併用している。
以下に、森田が呈示した「恐怖突入」に相当する症例の中から、「恐怖破壊法的」な治療例として、任意に3例を選んで、簡単に紹介する。
♥ ♥ ♥
〔心悸亢進発作例〕(『神経質ノ本態及療法』大正十一年一月稿)。
森田の恩師の某大学先生の夫人。多年、発作は夜間に多く起こって、横臥できず布団に凭れるのみ。往診をしたところ、今夜も発作が起こりそうだと言う。所謂「精神性心臓症」と診断して、次のような教示を授けた。「では今夜は最も発作の起こり易い横臥位をとり、発作を起こし、苦痛を忍びながら、発作の起こり方や経過を詳細に観察されよ。そしたら私は将来発作の起こらぬ方法を教えます」と。ところが患者は、発作を起こすことができず、朝までぐっすり眠ってしまったのだった。そこで森田は「これが体得というものです。従来は、発作を予期して、心惑い、徒らに苦痛を増大させていたのです。発作を逃れようとする卑怯をなくし、恐怖に飛び込んだので、発作はどこかへ去ってしまったのです」と説明してやったのであった。
♥ ♥ ♥
〔胃痙攣様発作例〕(『神経質ノ本態及療法』大正十一年一月稿)。
五十九歳女性。十年前に発病して、胃部に発作性に激痛が起こる。最近ひどくなり、朝夕にその発作がある。診察したところ、胃痙攣ではなく、ヒステリー球に近いものであった。発作への注意によって精神交互作用が起こり、予期感動から発作の起こる時刻まで定まっている。森田はこの患者を、大正10年3月に入院させた。そしてまず臥褥をさせて、次のように指示した。診察と治療のために必要だからとの口実の下に、予期の時間よりもなるべく早く、努めて発作を起こして見せなさいと。ところが、そのように命じると発作は起こらなくなってしまった。その後作業にも参加して、全治を迎えたのだった。
♥ ♥ ♥
〔強迫観念症の例〕(『神経質及神経衰弱症の療法』第三十六例)。
二十四歳、農家の未婚女性。十代後半より、自分が盗みをしたかのような窃盗恐怖や、火事恐怖など諸種強迫観念が起こり、家に閉じこもっていた。難治であったが、最も的確に治癒させたものである。患者は十五歳頃に呉服店で反物を新調したが、それを盗んだのではないかと気になり、箪笥にしまって着ることができず、ついには箪笥に触れることもできなくなっていた。大正10年4月より、2ヶ月の予定で入院療法を試みることにした。絶対臥褥を経て作業に移り、患者の苦痛の種となっていた衣服を国元から取り寄せさせた。入院して50日を経たある晩、突然森田は患者に、今夜この衣服を着て寝るべし、と命じた。今夜は当然徹夜の苦悶に悩むであろうが、その覚悟で忍耐しなさい、と命じた。然るに翌朝、患者は、昨夜はどうなることかと思ったが、案外何事もなく、いつの間にか眠ってしまった、と言って喜びに溢れていた。恐怖に突入して、恐怖の破壊を体験自得したのだった。掛け金が外れるような心境になったのである。その後患者は帰郷し、「気になることが出来ても、教えられた通りにやっています」と便りに書いてきた。この患者は、まもなく森田の家に来て、お手伝いとして立ち働くことになった。
♥ ♥ ♥
以上の症例のうち、はじめの2例は発作性神経症に相当するが、いずれも予期恐怖が働いて精神交互作用が高じていたところを、暗示的とも言えるような教示の下に、恐怖に突入させ、恐怖が破壊される体験に導いている。最後の強迫観念の例では、入院して数十日を経て、もはや後に引けず、森田に身を任すほかない段階で、恐怖になりきらせ、恐怖との対立から解脱させたのである。見事に巧んだものである。森田との強い絆が治療的要因になった例でもある。退院後森田家の従業員になったのは、その証左で、転移が続いていたと言えよう。
ここで想起するのは、雷恐怖の人に対する盤珪禅師の教えである。「驚きなばそのままにてよし、用心すればふたつになる」と盤珪は言った。恐怖は恐怖のままにして、恐怖と予期恐怖を対立させるなと盤珪は戒めたのだった。森田の場合は、わざとお膳立てをし、手の込んだ教示を用いて、意図的に恐怖に突入させているので、技法として不自然であったと言えるかもしれない。しかし、このような「恐怖破壊法」的な恐怖突入は、入院による特殊療法を始めた初期においても、療法のひとつの特徴をなしていたようである。熱意ある治療者の応援があったからこそ、患者は恐怖に突入して、「煩悩即菩提」、「煩悶即解脱」の境地に誘われたと言うことができよう。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
5. 家庭の不和による臥褥と「頓挫療法」について
さて、入院による余の特殊療法を改めて考えるとき、今ひとつ分かりにくいのは、第一期に絶対臥褥を導入した森田の着想や意義についてである。森田がその目的として、第一)診断上の補助、第二)安静による身心の衰憊の調整、第三)精神的煩悶苦悩の根本的破壊、の三つを挙げていることはよく知られているが、それが早くも大正9年の著作(「精神療法ニ對スル着眼点ニ就テ」)に記されていることは既述した。しかし、三項目のうち、第一の診断上の補助は、これ自体が補助的な目的としか思えない。したがって第ニと第三のふたつの項目を問題にすべきであることになる。
遡れば明治42年の著作において、森田は、強迫観念の病理について、その煩悶を理論を以て解脱させることは不可能であり、治療に難渋していることを告白的に記している。そしてその病理は仏教語で言うならば「繋驢橛(繋がれたる驢馬が廻り廻りて其杭にからまり動きも得ならぬ様」(禅語)に喩えられるとし、切に宗教家の示教を希うと、あからさまに書いているのである(「神経衰弱性精神病性體質」、人性、第五巻、第五-六号、明治四十ニ年五月-六月)。
その後の仏教的禅的な展開を知る資料に乏しいけれども、催眠や説得療法を試みても効果をあげ得なかった森田が、いよいよ煩悩になりきる道を治療的に探って「絶対臥褥」に到達したのではなかろうか。禅の形に当てはめるならば、座禅を臥禅にしたものが絶対臥褥だとも言えようが、論を座禅につなぐ禅本位論は問題を狭くする。絶対臥褥という人間として原始の状態にして、「煩悩即菩提」を体得させようとしたのであろう。「煩悩即菩提」を自分は「煩悶即解脱」と言い換えるとしたところにも、森田らしさや、信念や、さらに彼自身の解脱的体験も込められたニュアンスさえ伝わってくるのである。かくして、絶対臥褥の目的の第三を理解することができる。
さて、そうすると残る第二の身心の衰憊の調整という目的が宙に浮きかねない。だが、これにつながるであろう森田の断片的記述やエピソードがあるので、取り上げることにする。
♥ ♥ ♥
帚木蓬生氏は、著書『生きる力 森田正馬15の提言』の中に、次のように書いておられる。
「正馬がこの臥褥療法を思いついたのは、郷里の高知県の風習からのようです。土佐地方では昔から嫁姑の間にいざこざが起こると、どちらか一方が三、四日臥褥をする習慣があったそうです。臥褥が終わると、双方が歩み寄り、良い嫁姑の関係に戻るのです。」
典拠を記しておられないので不審に思いながら、高知にそのような風習があったのかどうか、高知の森田の生家から遠くない地区にお住まいの高齢の知人らに問い合わせてみたが、そんな話は聞いたことがないとのご返事ばかりであった。ただ森田がそのようなことを言ったことはあったようで、かつて戦後に東京で森田療法に関わったご経験のある高齢の某氏の話では、そんな伝聞に接した記憶があるが、真偽はわからないままだったとのよしであった。ちなみに『形外先生言行録』には、昭和3年頃に森田の下に入院したI氏が、森田は郷里の嫁姑のいざこざでどちらかが三、四日臥褥することがよくあり、それをヒントに臥褥療法を始めた、と言っていたという回想を記しているくだりがある。
嫁姑間のいざこざを臥褥で収まりをつけるというのは、高知のよく知られた風習であったかどうかはわからない。だがそれは森田の念頭にはあったようなのである。それをどのように読み解くかが問題である。そこで森田の著作を改めて読み直すと、似たような例として、家庭の不和で寝込む話が、繰り返し出てくることに気づく。
それは、いずれも「臥褥療法」についての説明の中に出ている。異なる三つの著作のそれぞれに、同じ文章の一節が嵌め込まれているのである。その一節では、前半部分で、愛児を亡くした母親の悲痛や事業に失敗した人の煩悶に臥褥療法を応用できると述べて、引き続き次のように記述しているのである。
♥ ♥ ♥
「よく聞く事であるが、或は家庭の不和のため、或は何か気にくはぬ事があって、一日も二日も寝込んだまま起きて来なかったといふ事がある。之は或は神経精神病性若くは変質性人格者の自然良能によるものかも知れない。即ち忿怒なり悲憤なり、總て激情は臥褥によって之を和らげる事が出来るのである。」
この同じ文章が記されている著作とは、次の三つである。
・ 「精神療法ニ對スル着眼点ニ就テ(承前)」、医学中央雑誌、第三三〇号、大正九年七月。
・ 『神経質及神経衰弱症の療法』、大正十年六月。
・ 『精神療法講義』、大正十一年一月。
上記の著作で、「臥褥療法」について述べられている内容は、かなり共通しており、要点はおよそ次の通りである。
臥褥している状態では身体機能が安静になり、精神活動も平静になる。不安や苦悶に関係する刺激や機会のない環境に隔離して臥褥させると、短時間で精神的落ち着きが得られる。
精神病で興奮状態の者を強制的に寝かせると、案外短時間で安定する。
また自験例として、ある中学生が試験に落第して躁状態になり、絶対臥褥を命じたら、奏効した。また別の中学生で、ある事件により激しい苦悶状態になったものに対して、絶対臥褥を命じたら、数日間で著効を見た。いずれも刺激を遮断した室内で臥褥させたもので、臥褥療法は一方から見れば隔離療法である。このような絶対臥褥により、病的な、あるいは負の感動は増幅することなく、消失する。絶対臥褥は、実に「頓挫療法」と言ってもよい、と。
この中学生の2例の経験から、自分は臥褥療法を種々の患者に生かして、効果をあげるようになった、と言う。
このような文脈から、家庭の不和のために寝込むという話が出てくるのである。その文中に、神経精神病性若くは変質性人格者との用語が出ており、これは語弊があるが、当時森田は神経質を分類上そのように捉えていたのであった。いずれにせよ、森田は臥褥と隔離によって、「頓挫療法」と言えるほどに自然回復力が起こることを経験的に知ったのである。そのことへの着目が、入院療法の第一期を絶対臥褥としたひとつの理由になったと考えることもできよう。
しかし、中学生2名の例や嫁姑のいざこざ後に寝込む話は、いわば対症療法的であり、森田が言った「感情の法則」だけでも説明できそうである。彼はすでに大正5年に、感情の特性について、感情は放任すれば自然に消失することや、感情は表出するに従い益々強盛になることを指摘していた(「常識に就て」、人性、第十二巻第四号、大正五年五月)。 したがって、以上の例や話が、自然療法として自発的活動を生かすこの療法の、原点になる絶対臥褥に見合ったものなのかどうか、疑わしい。
♥ ♥ ♥
森田はつとに、入院第一期の絶対臥褥の目的として、三項目を挙げていた。この三項目は、先にふれたように、そのままではまとまりを欠いていて、わかり難い。
ところで、昭和3年に出版された著書『神経質ノ本態及療法』における絶対臥褥についての記載を瞥見すると、従来通りに三項目が並べられているけれども、第二の心身の疲憊の調整については、感情の自然の経過による消失と説明されている。どうやら当初は、やはり感情の法則レベルの発想であったらしいことが判明する。
一方、第三の精神的煩悶、苦悩の根本的破壊については、これを「本療法の眼目」と記して昇格させており、「煩悶即解脱の心境を体得せしむるにある」としている。ちなみにこの著作の原本は、大正11年に執筆された学位論文であるが、それが昭和3年に単行本として出版され、全集に収められているものである。
ともあれ、系統的な入院療法は深い奥行きのあるもので、療法の開発後もなお、森田自身、試行錯誤を経験したであろう。療法もまた、森田と共に成長していったのである。
嫁姑のいざこざと臥褥という下世話な話が、療法の絶対臥褥につながったかどうかは重要事ではなく、関係があるとすれば、感情の法則のような生理的レベルにおいてであろう。そして、森田自身、絶対臥褥の第二の目的としていた衰憊(疲憊)の調整は、相対的に重視しなくなっている。森田は自身が唱えた三項目に、まとまりがないことに気づいて多少困惑していたのかも知れない、と言ったら憶測に過ぎるだろうか。
(<その三>に続く)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥