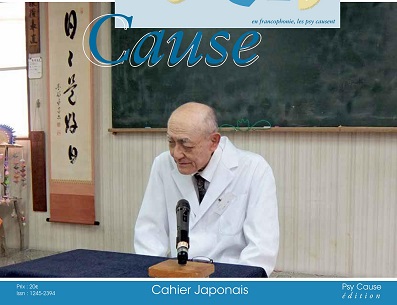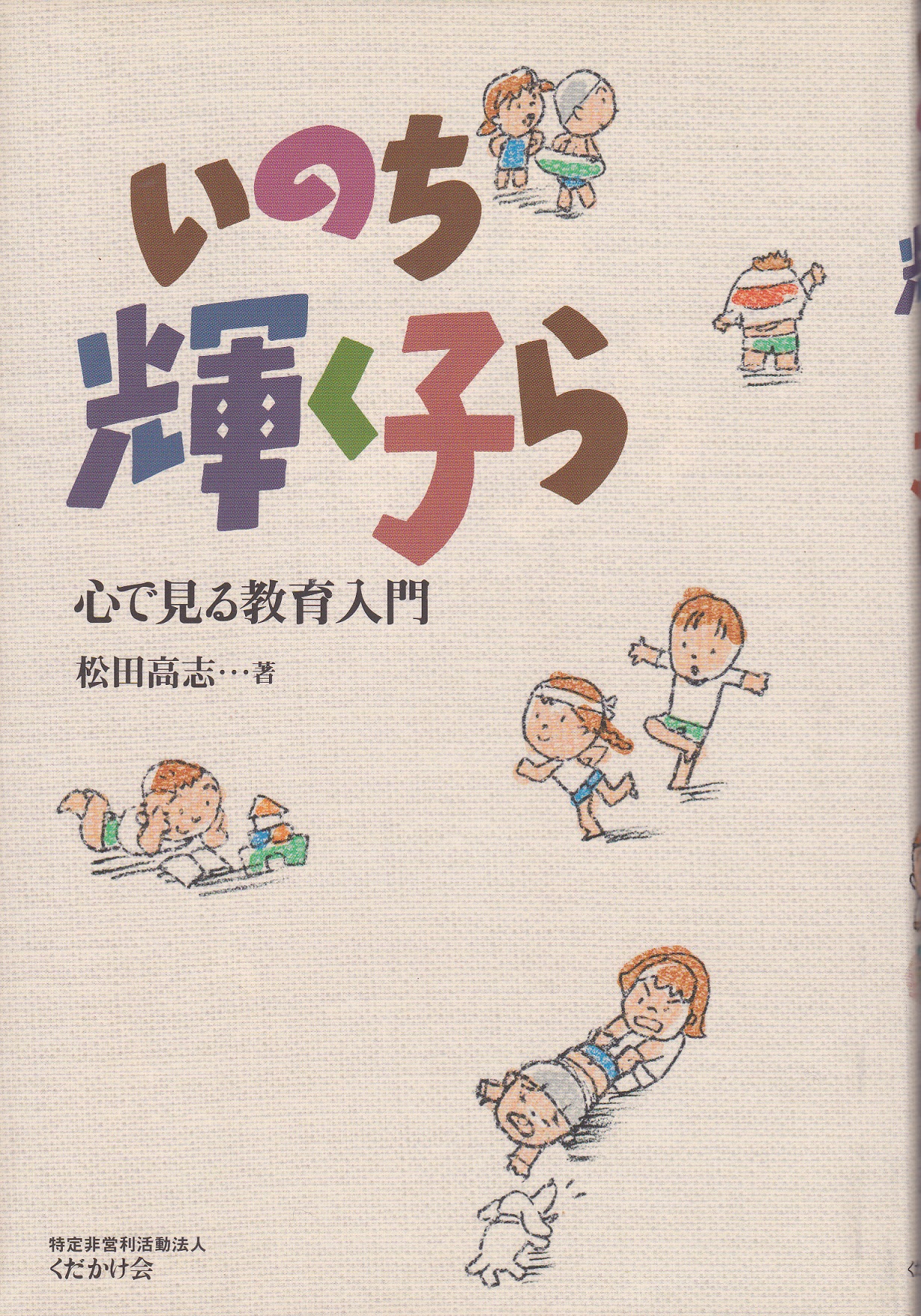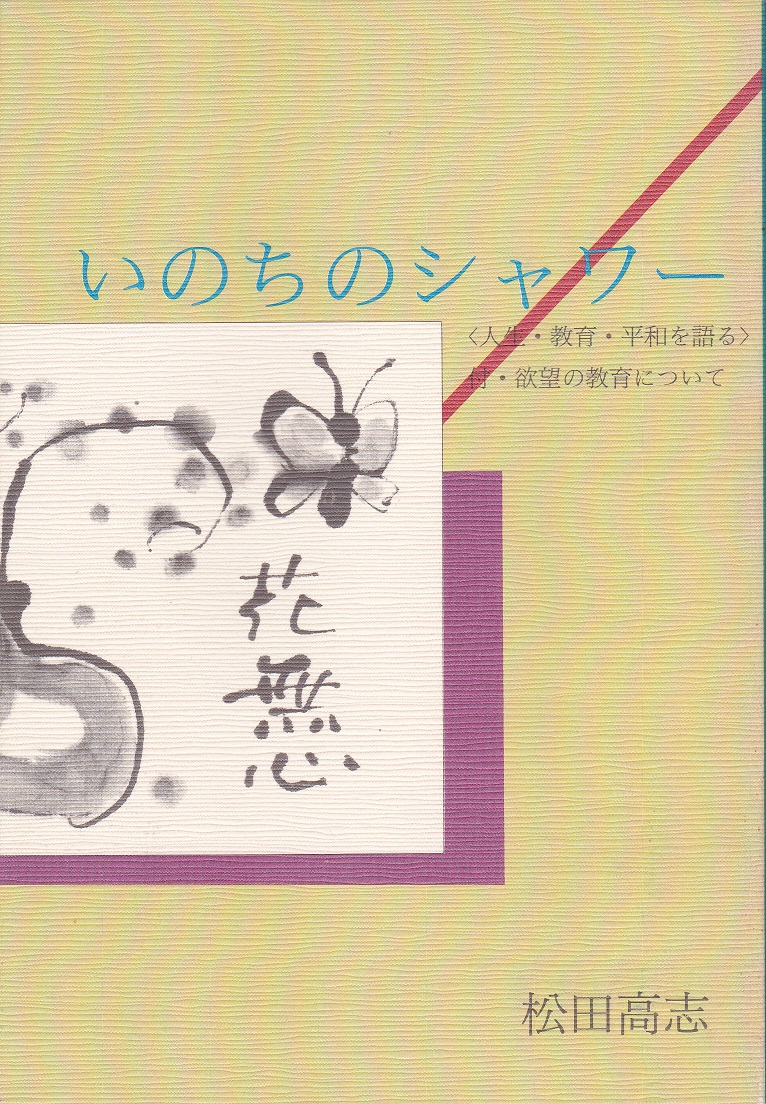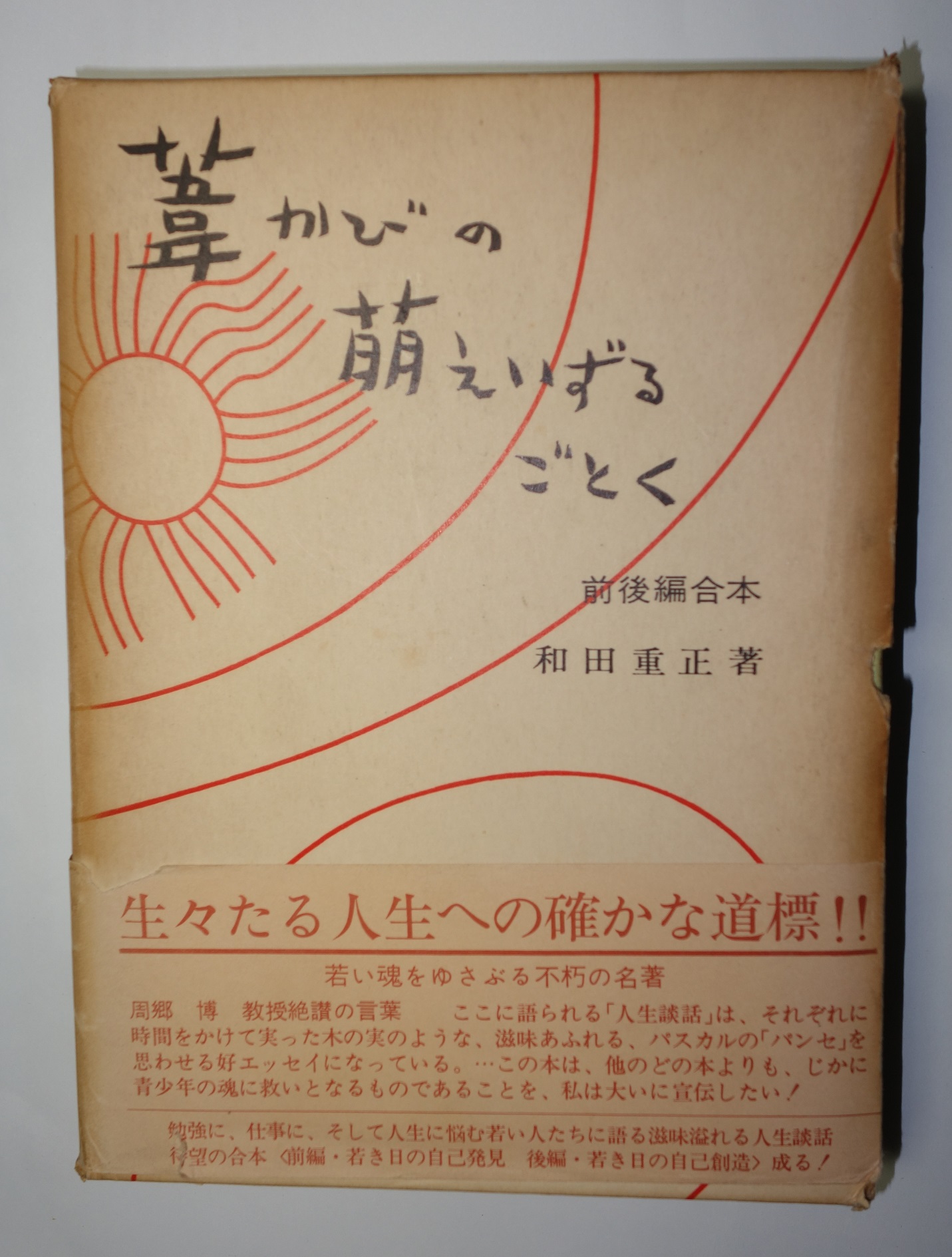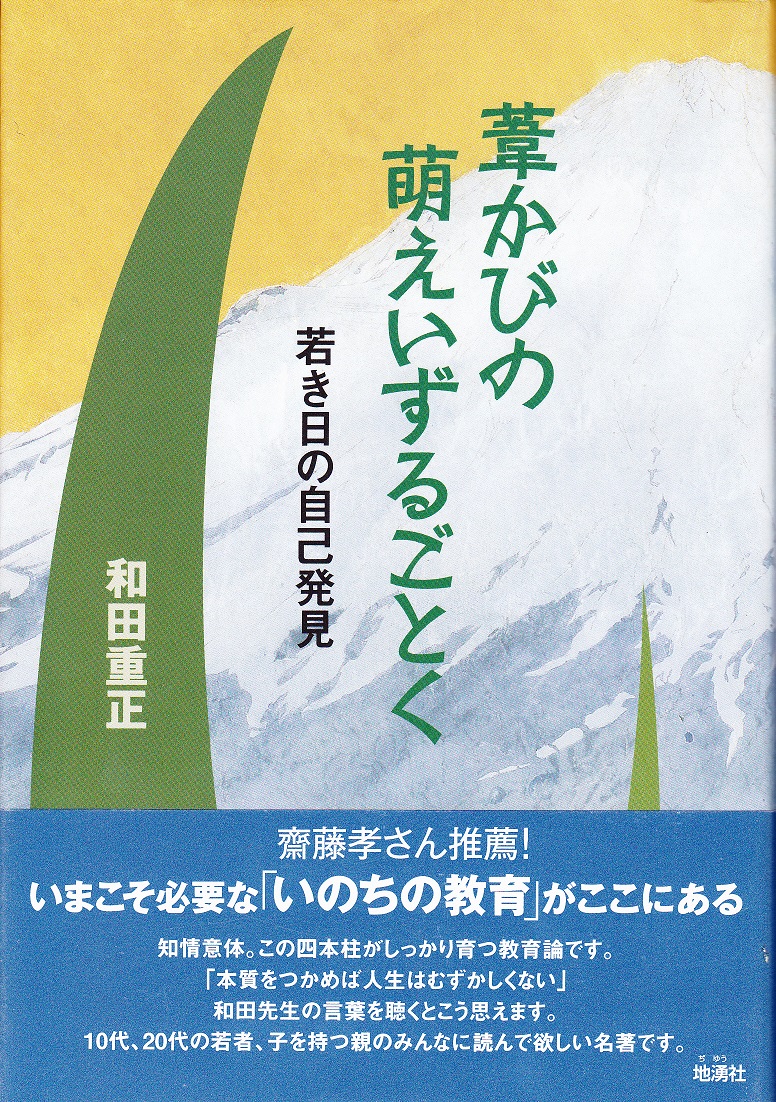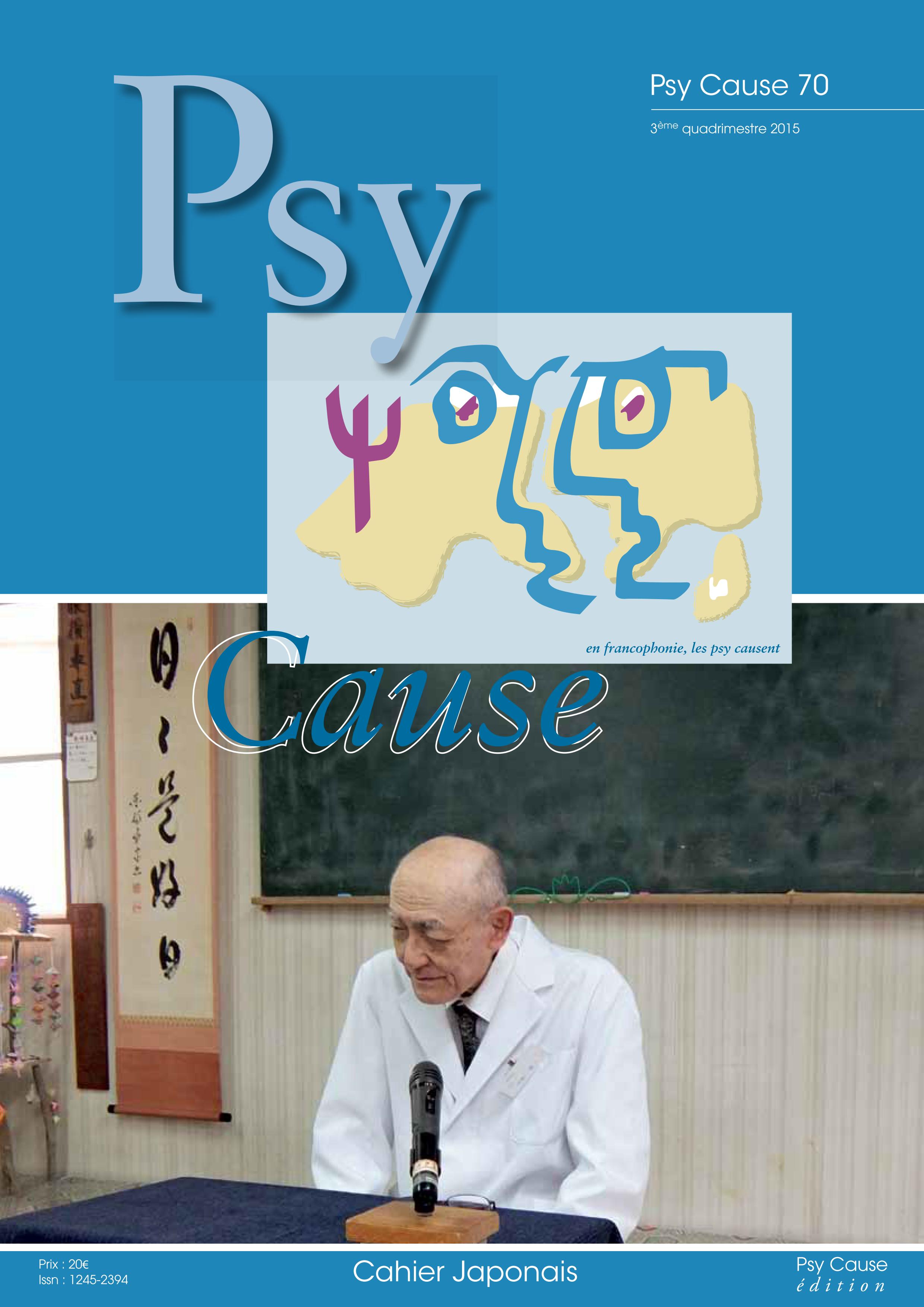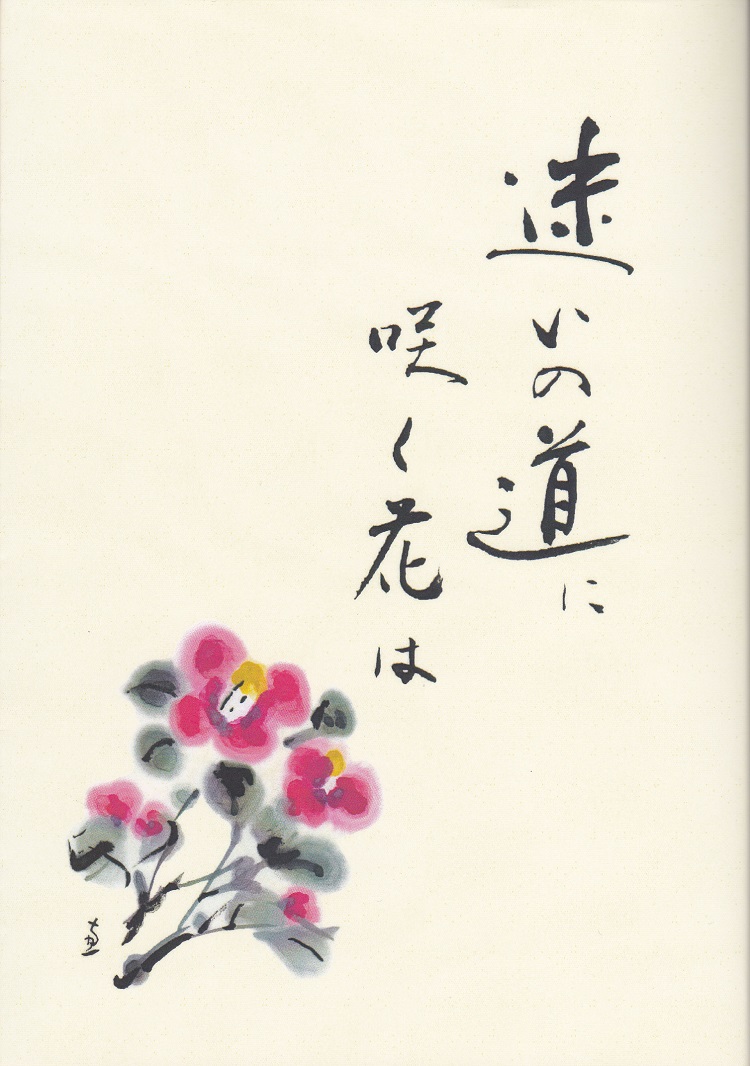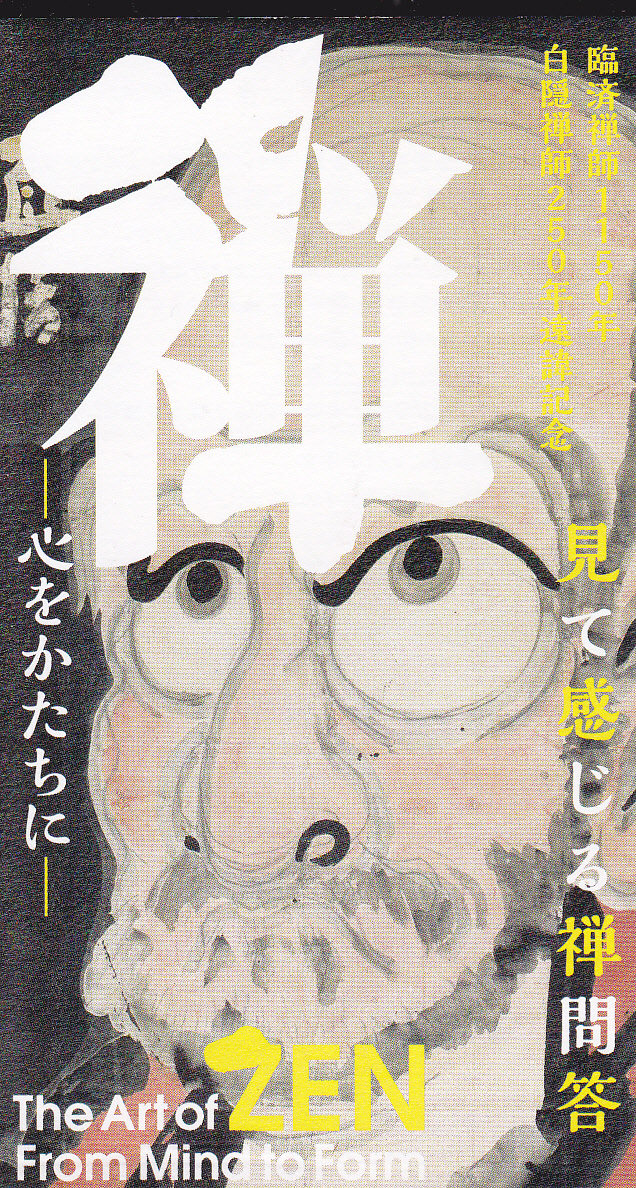「忘れられた森田療法(La Thérapie de Morita Oubliée)」―フランス語原稿(雑誌に既発表)の日本語訳―
2016/09/10
表題原稿のフランス語の原文は、雑誌 PSYCAUSE 70号の日本特集のうちの巻頭に掲載されました。それは、このHPの「研究ノート」欄から、原文でお読み頂けます。
しかし、森田療法のことについてフランス語で外国人向けに一体どんなことを書いたのかと、ご関心を持って下さる方もおられるかもしれません。今頃ふとそう思いました。そこで、遅ればせながら、日本語に戻した原稿をここに披露しておきます。何のことはない、お読み頂いたらわかります。
PSYCAUSE誌のこの日本特集は、一昨年秋、京都で開催された国際学会に基づいています。その際、学会参加者たちの三聖病院の訪問を受け入れる日程は予め組んでいました。ところが、彼らの京都入りとほぼ同時に、三聖病院の閉院が発表されました。かくして、PSYCAUSE学会の人たちは、期せずして、歴史ある三聖病院を訪れた最後の外国人グループとなったのでした。私の以下の一文は、そのような背景を視野に入れて草したものです。また立場上、あまり紙幅を取らぬように、特集の導入として短い小論を書きました。
しかしながら、あえて「忘れられた森田療法」―過去形でなく「忘れられる森田療法」と言うべきかも知れませんが―に執拗なまでにこだわり、既刊の小著と同タイトルにしたのには、訳があります。両者の内容は違います。しかし、そこに通じている私の思いは同じなのです。
どうも前口上が長くなりまして、あいすみません。
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
忘れられた森田療法 La Thérapie de Morita Oubliée
Shigeyoshi OKAMOTO
去る2014年10月、第10回 PsyCauseフランス語圏内国際学会が、「文化間の出会い」という基調テーマのもとに日本の京都で開催された。この国際学会のひとつの大きな目的は、日本の独自の精神療法である森田療法について、京都にあるその療法の伝統的な施設である三聖病院を訪問して、実際の診療を見学して直接それを学び、そのような見学体験を通じて討論を交わすというところにあった。
ところが、この三聖病院は、同じこの年(2014年)の12月末に廃院になることが、学会が開催される直前に公表された。こうして、学会のために海外からやって来たフランス語圏の人たちは、図らずも三聖病院を訪問した最後の外国人となったのである。
1.森田療法の「ひとつの終わり」
三聖病院は、森田正馬によって森田療法が創始された直後の1922年(大正11年)に、彼の弟子の禅僧で精神科医師の宇佐玄雄によって開設された(最初は診療所で、1927年(昭和2年)から病院)。その後、息子の二代目院長に受け継がれて、三聖病院は森田療法の最も伝統的なサバイバーとして、通算92年間、役割を果たし続けて、遂にその歴史の幕を閉じることになったのである。昨今の日本では、文化や文明のめまぐるしい変化に伴い、伝統的な森田療法を維持する施設は既に殆ど消滅し、とりわけ、禅を生かした森田療法の施設は、既に三聖病院だけになっていた。20世紀末以来、森田療法は、新しい時代の要請に応じて、入院よりも外来での治療が主流となり、薬物療法や他の精神療法と併用される方向へと変化していた。そのような新しい動向が進む中で、伝統的な森田療法を代表する専門病院であった三聖病院が、2014年末に閉鎖したことは、この療法の一つの終焉を象徴する出来事であった。
2. 森田療法の「本当の始まり」
ところで、三聖病院の廃院は、伝統的な森田療法の精神の終焉をも意味するのであろうか? 否、決してそうとは思えない。神経症的な病理に対して、禅寺におけるような作法や雰囲気を、薬の代わりに用いて暗示的に治療する療法は確かに終わりを迎えた。そして、それはまた、神経症の症状が禅的な「悟り」によって治ると思いこむ人たちを誘惑する〈迷妄の集いの場〉の提供の終わりでもあった。それらの終焉により、覆われて見えにくくなっていた森田療法の本当のエスプリ(本質)が、これを機に現れて、今後一層そのエスプリ(本質)が評価され、万人の人生の中にそれが生かされることが望まれる。
これまで、特に外国人に対して、森田療法は“神経質(SHINKEISHITSU)”の治療法として紹介されてきた。確かに、この療法を創始した森田は、神経質の治療である点を力説した。けれども、そのような表面的な力説のために、この療法に含まれているせっかくの深い本質が、日本においても見落とされがちになっていたことは否めない。まして外国人に対して、紹介に従事する日本人たちが、この療法の本質部分を慎重に説明することなく、単に“神経質(SHINKEISHITSU)”の治療という表層だけを紹介することで、おそらく誤解を与えていたに違いないことは、非常に残念である。
実際、森田がこの療法を、最初は“神経質(SHINKEISHITSU)”の治療法として開始したことは事実である。しかし “神経質 (SHINKEISHITSU)”の症状としての不安の心的メカニズムの中に、人間の存在に関わる根源的な不安が潜んでいることに気づいて、仏教的な智恵を療法に取り入れて、治療としての深みを増していったのだった。精神科医として診療に携わっていた彼は、概して“神経質(SHINKEISHITSU)”の患者を治療するに止まらざるをえなかったが、自分の療法はすべての人間の再教育だということも力説したのだった。
そこで、次にこの療法に含まれる二層的な意義について、さらに述べておく必要がある。それはまず “神経質(SHINKEISHITSU)” の治療法であったのだが、さらに神経質の患者だけに限らない、すべての人間の生き方に関わる深い智恵でもある。以下では、森田療法における、このような二層性について言及する。
3. “神経質(SHINKEISHITSU)” とその治療
森田療法は、人名が療法の名称になっている点で例外的な精神療法である上、“神経質(SHINKEISHITSU)”という日本語での名称を与えられた素質あるいは病理を治療対象にし、しかも禅と関係があるのも確かなので、外国人の方々にとって、この療法は、当然ながら大変理解し難いことであろう。そのため、ここで、まず森田が治療の対象にした“神経質(SHINKEISHITSU)”とは何かについて説明する。それは決して森田自身の新しく作った用語(新作語)ではなく、ドイツ語圏の精神医学の用語“Nervosität”の日本語への訳語であった。それは、ドイツのクレペリンKraepelinによる、彼の独自の精神医学体系の中で、ある一つの病的な性質を表す用語として規定されていたものであった。その用語と概念は、Kraepelinの下に留学した東京大学の精神医学の教授の呉秀三によって、日本に導入された。呉の弟子だった森田は、主に彼からそれを学んだのであった。そして森田は“Nervosität(SHINKEISHITSU)”の特徴としての素質や症状を知った上で、不安に傾き易いその素質が惹起する心気的な悪循環の心的機制に焦点を当て、その悪循環によって症状が固定化するというかなり力動的な捉え方を示した。こうして、“Nervosität”の概念を踏襲しながら、その精神病理について柔軟な理解の仕方をする立場から、森田は彼独自の療法を創案したのである。結局、“神経質(SHINKEISHITSU)”という用語は、“Nervosität”の訳語以外の何でもなかったが、その精神病理を、クレペリンよりも柔軟に捉えたところに森田の卓見があったのである。
とは言え、森田の捉えた“神経質(SHINKEISHITSU)”とは、神経症になりやすい素質あるいは神経症そのものと別のものではない。一般にこのような心性においては、人一倍、不安に対して敏感で、不安を治そうとして、かえって不安に埋没して、生活が膠着し、クオリティ・オブ・ライフを低下させるばかりとなる。そこで、森田療法では、不安が治らなければ治らないまま、ただそのまま生活するように、治療者患者関係の中で言葉少なに促す。解決しない心を引きずりながら、歩き出す中で、新しい花が咲いたり、実がなったりするのである。
4.人生の苦悩に対する森田療法
神経質や神経症の精神病理に起因せずとも、誰しも人生に苦しみを体験する。そのような避けがたい苦悩に対処する、森田療法の第二の層について述べておきたい。
仏教によれば、人間はこの世で八つの苦の試練を受けるさだめにある。
第一の苦は、「生」そのものである。生がなぜ第一の苦なのか? 人間は自分の意志によって、生まれてくるのではなく、絶対受動的に生を享ける。親も、先天的な心身の素質も、境遇も、一切自分の意志で選択することはできなかったのである。生まれてきた自分の存在理由を理解できなくても、生への執着が起こる。だが、日常生活の中で、種々の不合理な体験をすることは多い。そのために人生に懐疑的になり、不遇な運命に対するルサンチマンが起こる。このような生の苦は、人間の存在そのものにかかわる最も根源的な苦である。第二は、「老」の苦。第三は「病」の苦。第四は「死」の苦である。八苦のうち、以上の前半の四苦は、人間の存在の根源にかかわるものである。
第五は、愛する人との別離、第六は憎悪すべき相手との邂逅、第七は求める対象を得ることの不可能性、第八は、心身の活動に伴う煩悩や葛藤である。これら後半の四苦は、日常の生活の中で体験されるものである。
以上の八苦は万人にとって不可避なものであり、それゆえにこれらを否認せずに受容して、生きることを仏教は教えている。
苦は楽を生み出し、楽は苦の種になる。両者は剥がし難い表裏一体のものである。仏教はもっぱら苦に虐げられて生きることを強いるのではない。苦にも楽にも素直に一体化して、自然のままに生きるところに人間の自由があることに気づくのが、仏教の智恵なのである。
どんなに科学技術が進歩して社会生活の利便性が高まり、先端医療が開発されて、新しい治療が発見されても、人間は必ず死を迎える。にもかかわらず、科学の進歩は、人間に錯覚的な万能感を与えた。そのような万能感と、仏教の示す八苦との間の懸隔は広がっていくばかりである。現代人のメンタリティの特徴として、苦に対する耐性が低下しており、心的外傷に過敏になっていて、それを弾力的に受け止めて自己修復する柔軟な機能である、いわゆる “レジリエンス” の力に欠けている。現代人は他者の攻撃性に対して、容易に挫けるか、あるいは反撃する習性を獲得してしまった。他者を友とみなさず、他者は敵とみなされがちである。残念ながら、他者は敵対者の属性を帯びていることが多いのが現実である。日本では、子どもたちは集団で、弱い子どもをいじめ、いじめられた子どもが自殺する事件が後を絶たない。学校の教員たちも、親たちも、子どもの教育に責任を持とうとしない。大人たちの自殺も頻繁に起こり続けている。これが、生きることを重んじる森田療法を生んだ国、日本の現実である。
神経質や神経症の治療を、病院やクリニックの診察室でおこなうことも必要だが、森田療法は、狭義の精神療法であることから脱皮して、教育や福祉や企業の中に浸透することが望まれる。しかし、それは教条としての森田療法を押しつけようとするのではない。森田療法は、本来専門分野たりえない筈のもので、権威的な専門家を必要としない。たとえ専門家がいたとしても、他者の苦悩を救い、他者を教育することは容易なことではない。ではどうするのか?そのように自分に問いかけることが、契機となる。そこで人は自分と自分の置かれている状況を見つめれば、素直な心に目覚める。素直な心に目覚めたら、やむにやまれなくなって、何かに向かって動き出さざるをえなくなるであろう。
こうして第一歩を踏み出すのである。その歩みは、自己のためか他者のためか分かち難い自然な動きである。治療者対患者という役割的関係も消滅する。
こうして、精神療法の枠を出て、森田療法という名称さえ失い、苦悩をもつ人間同士として出会いを経験するところに、森田療法はその深みを増していく。
このような森田療法の本質的な部分は、今日までほとんど忘れられていたように見える。療法の本質を含みながら、同時に形骸化してもいた伝統的森田療法が衰退して、その歴史に幕を下ろした今日、そのエスプリ(本質)が改めて思い出されて、森田療法にとらわれない森田療法の静かなルネサンスが新たに始まるであろう。


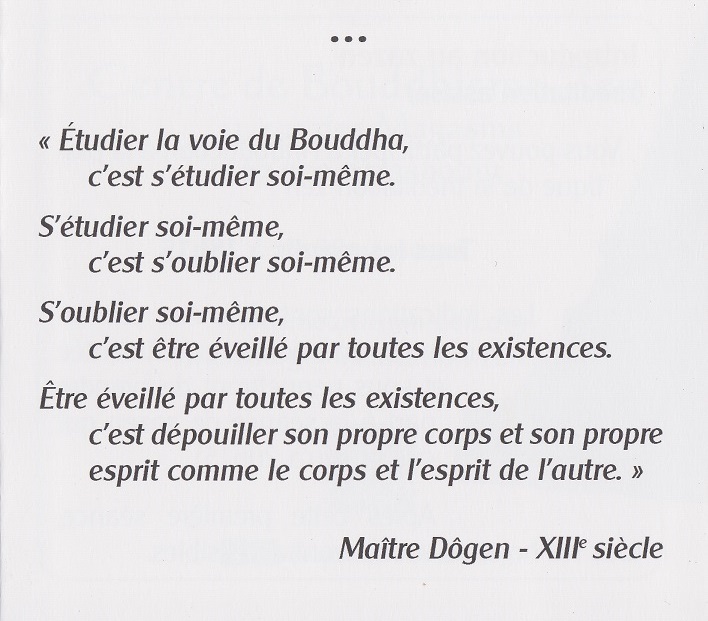


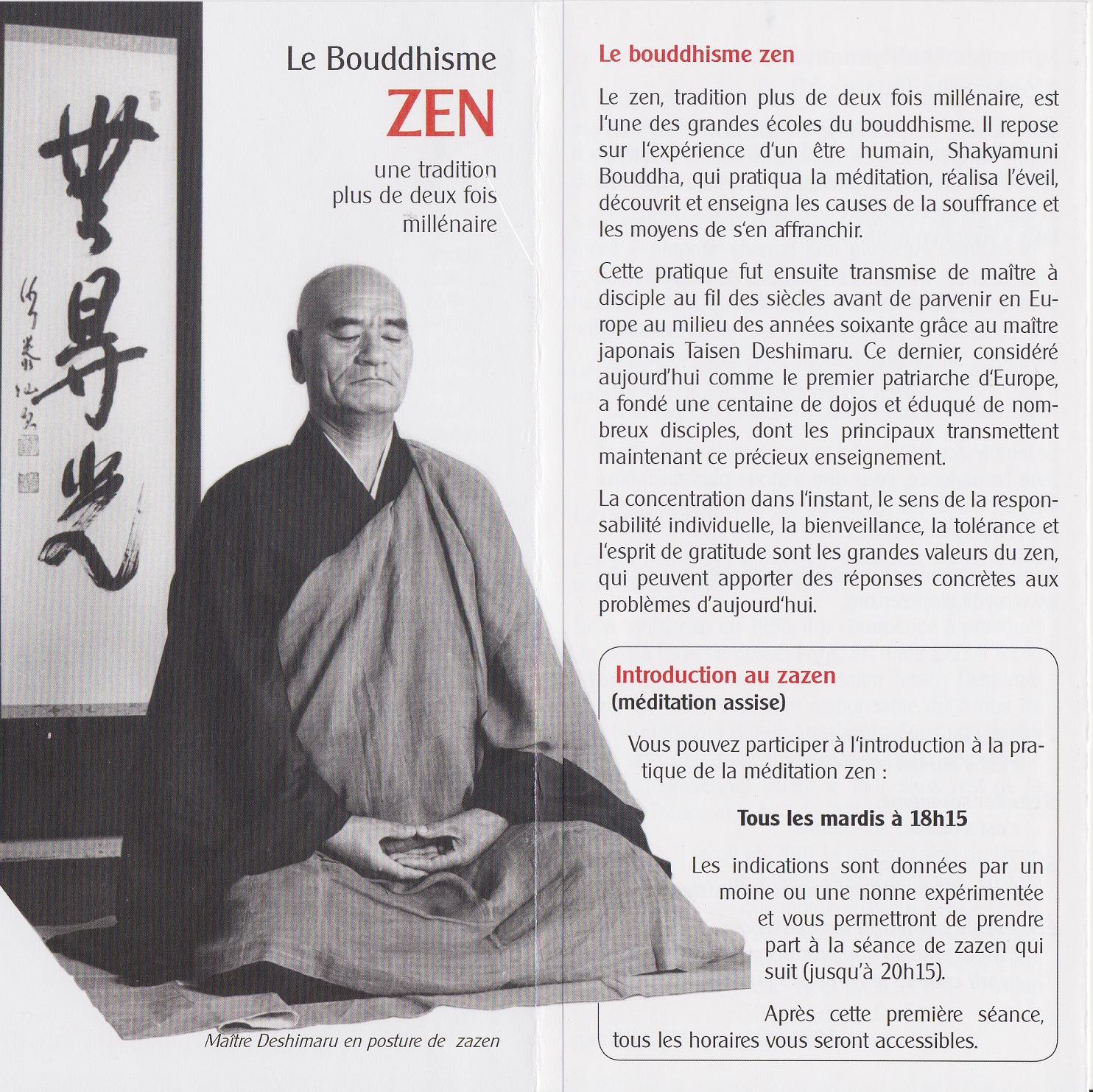
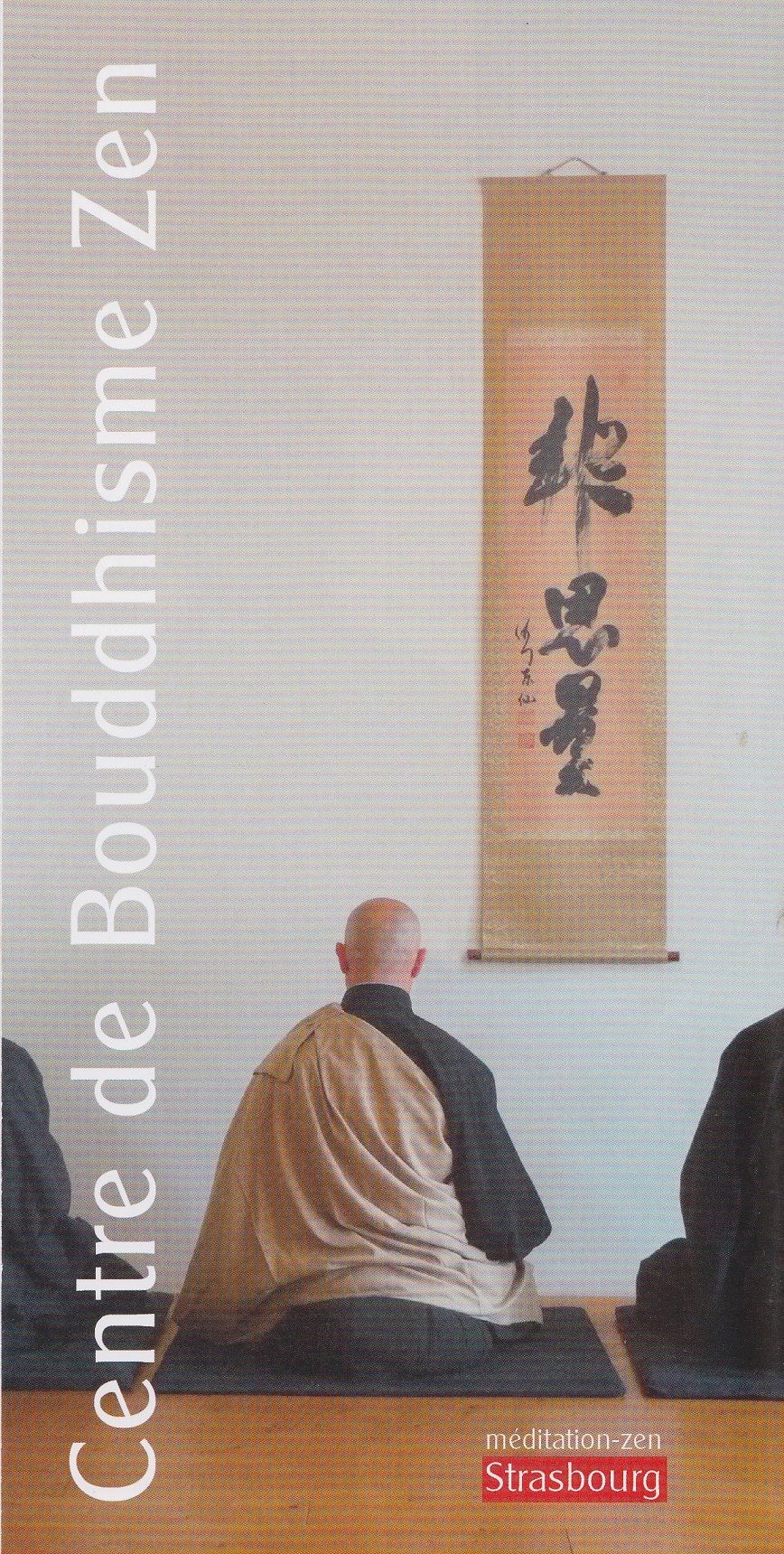


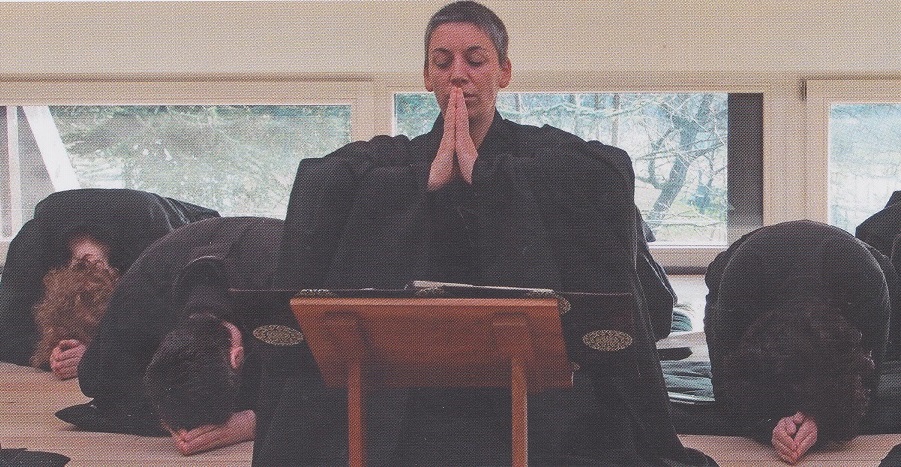
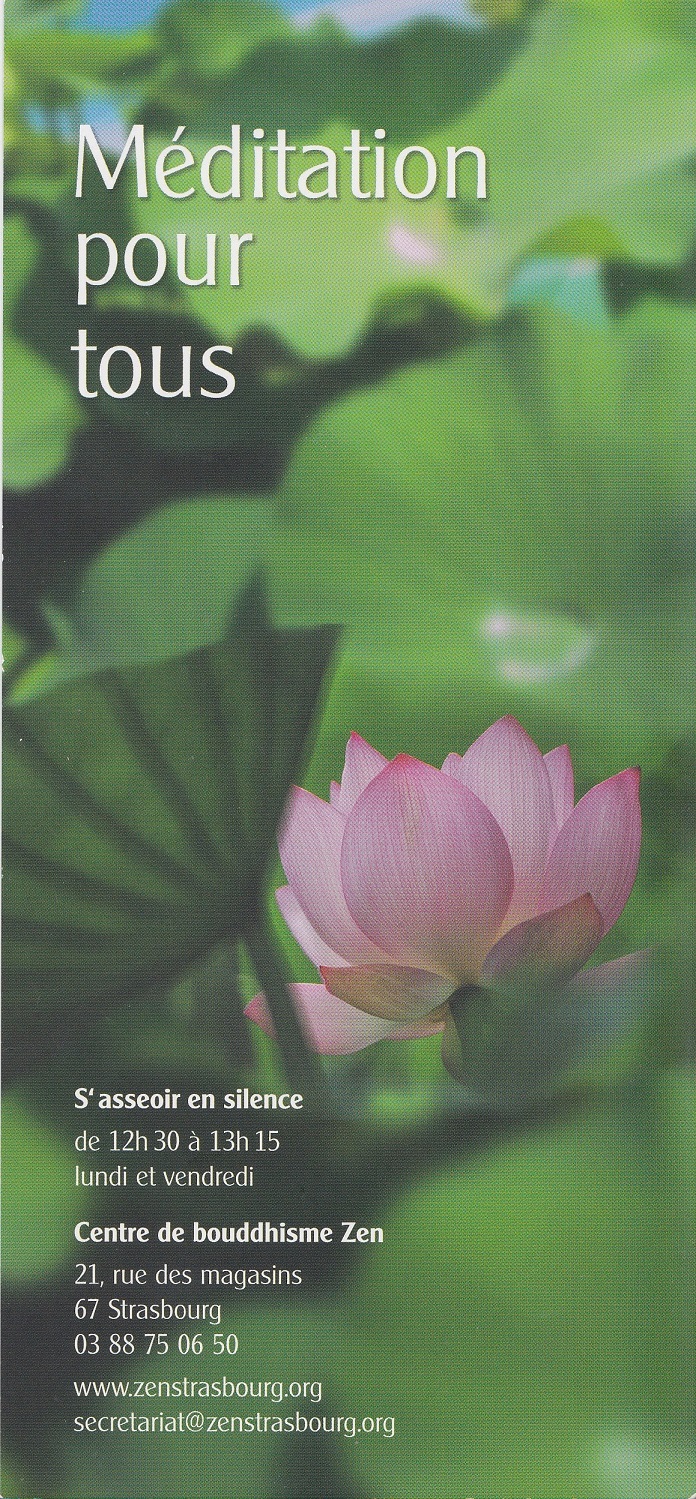


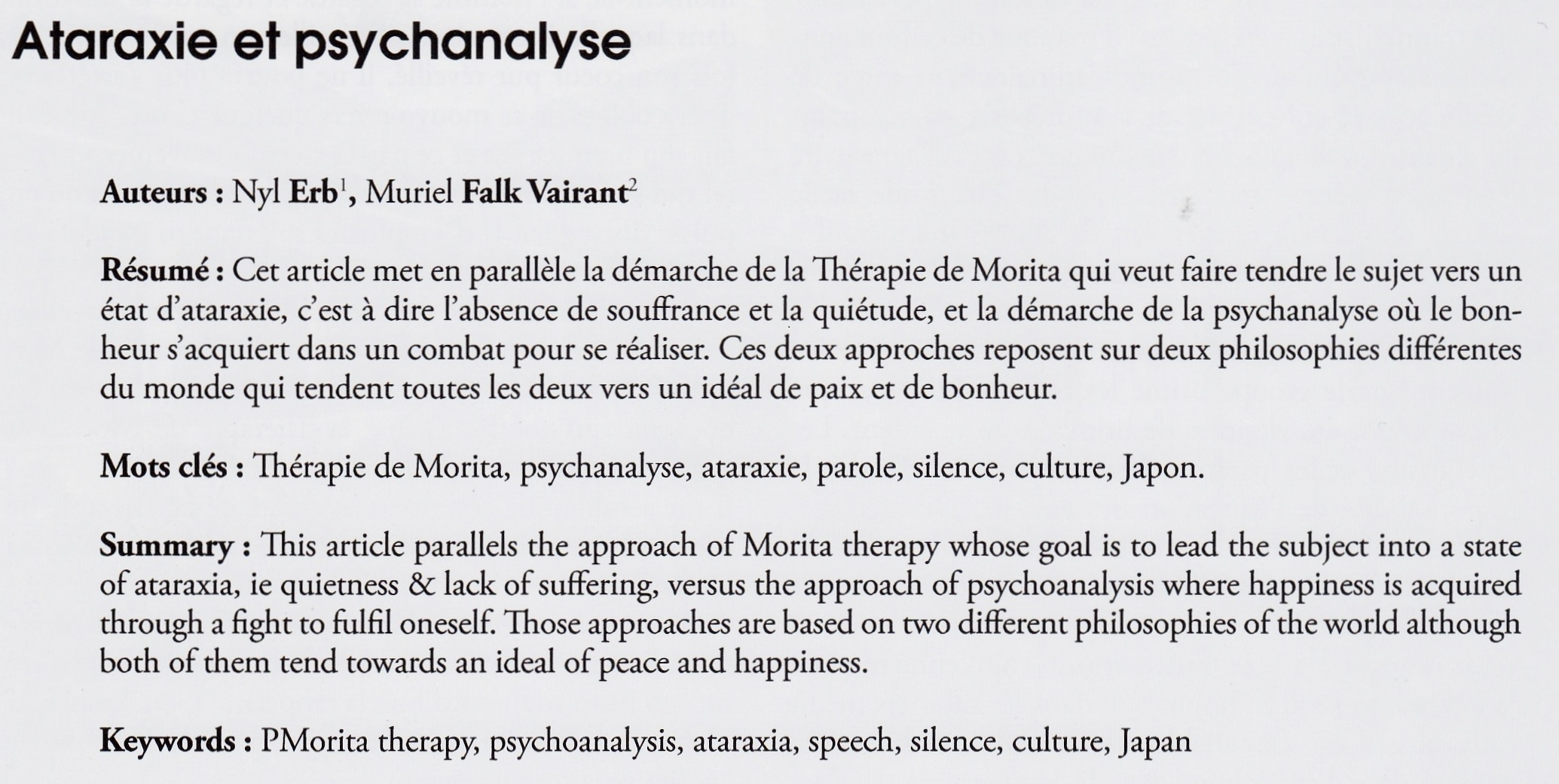
![puse_02[1]](http://kyoto-morita.org/wp/new-blog/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/puse_021.jpg)
![072509[1]](http://kyoto-morita.org/wp/new-blog/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/0725091.jpg)