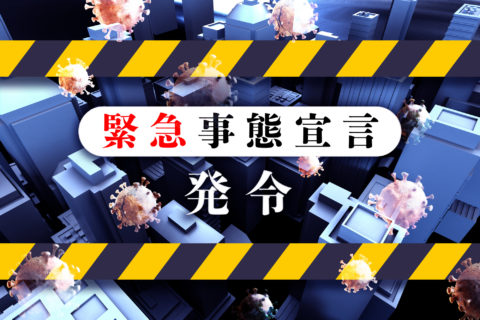コロナ危機の時代の森田療法(上)―コロナ元年、私たちの受難―
2020/06/14

コロナ危機の時代の森田療法(上)
―コロナ元年、私たちの受難―
1. コロナ元年
令和の2年目はコロナ元年になった。新型コロナというしたたかなウィルスが登場して、人間がこれと共存して生きねばならないという、未曽有の試練と遭遇した、恐るべき元年となった。
森田療法は、神経質の治療を端緒に始まった精神療法だが、単なる精神療法ではない。森田は「事実唯真」と言い、「自然に服従し、境遇に従順なれ」と言った。現実世界の、事実としての出来事、現象のすべてが、真実に他ならない。どんな不条理なことも、すべてが真実である。それが自然のことわりなのである。花鳥風月ならぬ、厳然たる自然の事態に服従して、その境遇に従順に生き抜け、と森田は教えてくれた。それは単なる神経質や神経症の症状の治し方をはるかに超えた、生きるということの教えである。
人生は苦である。仏教では「生老病死」の四苦と言う。生を受けて生きれば、老いがあり、病に罹り、やがて死ぬことを避けられない。そしてその過程では、愛する人との別離や、欲しいものを求めても得られない苦しみなどを体験する。合わせて「四苦八苦」である。
釈尊も親鸞も白隠も強迫観念に悩んだ神経質者だったと、森田は言っている。強迫観念に正確に当てはまるかどうかは、まあわからないが、実存的な深い悩みだ。ともかく、森田が教えてくれたこと―。それは、悩みを生きた先人たちが仏教の貴重な叡智を生みだした。そして、神経質者に限らず、苦や煩悩を有する私たち万人がそれに学びうるということなのであった。
今、コロナ元年、間違いなく新たな苦難が始まった。予想だにしなかったような悪夢が現実の危機として、今ここにある。森田療法はこの状況にどう対応するのか。いや、そのような対岸の火事を見るような問いを立てること自体、おめでたいことかもしれない。第一線の医療に携わる方々の献身的な努力をはじめとして、さまざまな分野で多くの人たちが、森田療法を論じるまでもなく、コロナに対処する直接間接の必要事に取り組んでくださっている。そこに生きた森田療法がある。必要上とは言え、森田療法に研究的に関わっている私たちには、かなり後ろめたい話なのである。
2. コロナ狂騒曲
1月下旬に横浜を出航したクルーズ船が、2月初めにウィルスとその感染者らを乗せて帰還し、横浜港に停泊した。あたかも黒船を迎えたごとく、この国の関係者は周章狼狽した。しかし、集団としての国民の心理は、危機に対して遅れて反応する。人びとの大半はテレビの画面にライブで映る大型船の姿をお茶の間劇場で他人ごとのように見入っていた。
その後のことは言うまでもない。危機に対して遅れて反応する分だけ、冷静さが失われる。パニック反応が始まった。不安、恐怖、反動としての無関心や否認、感染者に対する無思慮な差別や非難。外出の自粛が要請され、自宅での巣ごもり中には、DVやアルコール依存症が問題になった。それは経済生活を襲った危機と無関係ではない。
行政は市民のためである以前に保身的である。私は京都に近いA市に在住し、市役所の近くに居住している。4月某日に私は必要があって市役所に出向いたが、何かただならぬ雰囲気を感じた。その翌日、NHK総合で、A市市役所でクラスターが発生、というニュースが伝えられたので驚いた。市の役所は市民が利用する所である。クラスターが発生したら、まずそれを市民に伝える必要があろう。内部の感染者数が、クラスターと呼ばれるに足る一定人数に達しても、明らかな報道はNHKの全国放送が先を越した。集団感染はそれ以前から始まっていたことになる。そしてクラスターが報道されて10日ほど経ってから、A市市役所は庁舎を全面閉鎖した。すべてが後手の対応だった。A市を含むこの県の県民性もある程度、背景にあるかもしれない。感染者の人権が守られねばならないのは当然である。個人情報を開示したら、差別対象となり、本人や家族は生きづらくなる。そのためかあらぬか、行政内のクラスター発生の情報提供にも、行政は謙譲の美徳を発揮した。役所の近所に住む者には、灯台もと暗しだった。
私はフランス人の知人(精神分析家)と親しくメール交換をしている。なので、フランスの情報の方が届いてくる。既に2月の時点で聞いたことだが、私たちの共通の知人(精神科医師)の勤務するフランスの精神科病院で集団感染が起こり、入院患者と職員ら、数十人が感染し、精神科医師1人が死亡したとのことであった。精神科病棟はまさに三密の環境であり、患者さんたちはしばしば自己管理能力に欠ける。はたして、その後わが国のいくつかの精神科病院でもクラスターが発生した。精神科の入院治療の場では、感染症に対する万全の予防対策を常に講じていることは容易ではない。その上クラスター発生後の対処には大きな困難が待ち受けている。それは、福祉施設の現場における問題に、ある程度通じるところがあるようだ。いずれにしても、一層の備えが必要であろう。

3. エッセンシャル・ワーカーの人たちに花束を
全国の医療従事者たちは過酷な状況に置かれている。この人たちに対して国民は感謝のブルー・インパルスを贈りながら、同時にウィルス運搬者としてその人たちを忌避している。ずいぶん勝手なことだと思うが、人間はそんなものらしい。6月10日時点での、全国の医療機関における集団感染は102件、医師、看護師の感染は550人以上になるということを厚生労働相が述べた(6月11日、共同)。全国の累計感染者数に照らすと、医師、看護師の感染者はその約3%を占める勘定である。コロナの診療の第一線で働く医療従事者数を分母にするならば、感染確率は一段と高い数字になる筈である。感染リスクの極めて高いそんな現場で働いてくださっているのだ。
森田正馬は、職業というものについて、色紙に次のような教えの言葉を揮毫している。 「職業によりて人の品性の定まるに非ず 従事する人の品性によって其職業は尊卑を生ず」。森田の教えはこのようである。その意味するところはおよそ理解できるが、よく考えると疑問も起こる。ひとつの理解として、なまじ地位が高そうな職業についても、それにあぐらをかいて、自分の品性を磨かなければ、その職業まで怪しくなるという警句である、と受け取ると分かりやすい。
むしろ逆に、職業自体に尊卑というものがあるように、私は日頃から思っている。誤解を避けるために説明をせねばならない。車に乗らないので、電車で移動する私は、駅の公衆トイレに立ち寄ると、そこで黙々と清掃をなさっているおばさんたちの姿を見かける。私はこの人たちに敬意の念を抱いている。汚く、きつい仕事のひとつである。汚いものは汚い。でもそのような清掃を誰かがしてくれるから、社会生活が無事に動いている。以前に、「羽田空港が世界一清潔な空港である理由」として、ベテラン清掃員のNさんのことが、テレビなどで取り上げられた。Nさんは若いときの苦労を経て、清掃のアルバイトに出会い、最初は「生きるため」に働いていたが、やがて清掃の仕事にやりがいと楽しさを見いだしたという。そうは言っても、駅の公衆トイレの清掃員の皆の方々が、楽しくてしておられるであろうか。汚いけれど、きっと嫌々、必要なことをなさっているのだろう。それが尊いのである。
便所掃除は分かりやすい例だが、人間社会が維持されるために、それを根底で支える不可欠な職業がいくつもある。コロナ禍のもとで、そのような職業がクローズアップされた。 農業、食品、交通、流通、電力、清掃などなど、そしてもちろん医療もだが、それらがその不可欠な職業に相当する。このような職業内容の仕事の従事者は、エッセンシャル・ワーカーと呼ばれている。
エッセンシャル・ワーカーの仕事は、しばしばきつく、汚く、ときには危険を伴う。そんな仕事に本気で従事なさる人たちが社会には必要なのである。
人間が人間らしく生きるために、同じく必要不可欠なものとして、さらに教育や文化がある。ただし緊急度の違いはある。このように見てくると、社会的な有事のときに見直されるという要因を含めて、職業に尊卑があるという見方はありうると思う。日頃光が当たらないが、尊い職業があることに気づくことが重要である。そしてそのような担い手に改めて感謝したい。
尊卑の卑の面もある。事実上の賭博、その他人間を依存症に陥らせて利を得る業種がある。これは、主に国家が責任を受け止めてほしい。
(中)に続く